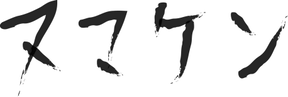<非対称性>『アメリカン・スナイパー』について
・第二回目のコラムを書こうとしている。
というか、じっさいに何度も書こうとしていた。
けれど、なにかちがう。
前回は、恣意性について、と題して書いた。
第一回目はいいのです。
点だから。
でも第二回目、
次の点を打つと、点と点が線になり、
それは方向を示します。
だからつまり、きっと、問題はその「方向」で、
この一週間で進もうとしていた「方向」が、
僕の旧知の方向ではなかった。
一週間、「次のコラムがあるぞ」ということで、
自分の知らないことをいろいろ調べようとしていたけれど、
けっきょく、知らないことはうまく書けないのです。
というか、それは単なる「解説」になってしまいがちで、
自分にとって親しみある言葉として発せられない。
だから、要するに、あまりおもしろくない。
もっと大事なことが、あったはずなのに、
という気持ちを、解消することがなかなかできませんでした。
・日曜の夜にレイトショーで『アメリカン・スナイパー』という映画を観ました。
観終わって、とても重たい気分でした。
その『アメリカン・スナイパー』という映画は、
アメリカにおいて賛否両論巻き起こしている映画とのことです。
アメリカのイラク戦争における、ある狙撃手の話で、
なんとこの狙撃手は、160人以上もの敵を殺した、という「伝説の英雄」なのです。
もちろん、ここでいう「敵」というのは、イラク人のことです。
もっというと、主にイラクの「テロリスト」と呼ばれる人たちのことです。
そして「テロリスト」というのは、民兵のような存在だけじゃなく、
ただ普通に暮らしていただけの人、女性や子供も、
武器を手に持って(アメリカを)攻撃しようとすれば「テロリスト」になるのです。
だから、主人公の「英雄」は女性や子供も、
もし攻撃の意志を見せたならば、撃たなければならないのです。
もし撃って女性や子供を殺さなければ、
仲間のアメリカ兵士が殺されてしまうからです。
映画はとても過酷なものでした。
映画が「過酷」というのは、つまり、
観ながらとても「過酷な気分を共有した」ということです。
この主人公の「英雄」、クリス・カイルという名前の人物は、
イラクからアメリカへ帰国しても、
戦場を体験する前のようにおだやかには生活できなくなってしまいます。
ニュースなどでたまに聞く「PTSD」といわれる症状のようです。
そしてクリスは、彼の家族とも心を通わせられなくなってしまうのです。
クリスの「物語」は悲劇的な最期で幕を閉じます。
ある意味でそれは、「物語」として「完成」されたことを意味するように思えました。
問題は、しかし、この「物語」ということだとも思いました。
・クリント・イーストウッドという人が監督したこの作品は、
徹頭徹尾、「アメリカの物語」でした。
「ひとりのアメリカ人」そして「その家族」の「人生」についての映画だったのです。
たぶんここが、賛否の「否」の部分になっていると思うのですが、
つまり、イラクの人の側の物語はまったく描かれていないのです。
僕はこの「描かれなさ」は、「あえて」やっていることなのか、
ということがとても気になるのです。
イーストウッドという監督、あるいは脚本家、製作者たちは、
そういう<非対称性>について、自覚的ではない人たちなのでしょうか。
映画では途中、ムスタファと呼ばれるイラクの側の狙撃手が出てきます。
このムスタファは、主人公のクリスと同じように、
あるいはそれ以上に、正確無比な狙撃をしてくる「強い敵」
(なんとオリンピックの元メダリスト)として登場します。
そしてある面でこのムスタファは、クリスという存在の「イラクバージョン」なのです。
映画では、一瞬ですがムスタファの妻と子供が映るシーンがあります。
それは、ムスタファ(イラク)にも、クリス(アメリカ)と同じように、
守るべきものがあって戦っている
ということを暗示するものだったように思いました。
全編にわたってリアリティが満ちていたこの映画で、
このムスタファという存在だけがなにか「空想的」な余韻をのこします。
とても「意識的」な存在のように思えたからかもしれません。
最初から最期まで、ムスタファはひとこともしゃべりませんでした。
ただ、重要そうな暗示をしめして、消えていきました。
この映画はクリス・カイル本人の自伝的著書を原作にしています。
つまりイーストウッドたちは原作を映画にするにあたって、
物語を相対化させるためにこの(原作にない)ムスタファを登場させたのだと思います。
そこにはいろんな意図があるのだと思います。
・この映画で描かれているような現実、
状況というのは、しかし、他人ごとではまったくないと思うのです。
「アメリカ」や「日本」という国単位で考えるのでなく、
「世界」をまるごとひとつの国として考える、
自分もその一員である、
というような思考が、もしできるとしたら、
どこに何が偏っているのか、
誰が比較的多く大声でしゃべっていて、
誰が比較的常に無言で黙っているのか、
どこに泣いてる人がいて、どこに怒ってる人がいて、
それは、いったいどういう理由なんだろう、ということが、
一国の内側で考えているよりも、もっと広く公正に考えられるはずです。
もちろん、「広い」ことがただいいことだとは限りません。
小さい、ごく身近なところ、僕たちの生活の近辺にも様々な<非対称>があるはずです。
それでも
芸術が欠如すること、
物語が欠如すること、
それは、決定的な「人間性に対する無理解」を生むのではないでしょうか。
中東の現状はそれを証している気がします。
((対称性を、取り戻す方向に息をふきかけるんだ))
((それができなきゃ無意味なんだ))
2015/02/24 9:49 記
というか、じっさいに何度も書こうとしていた。
けれど、なにかちがう。
前回は、恣意性について、と題して書いた。
第一回目はいいのです。
点だから。
でも第二回目、
次の点を打つと、点と点が線になり、
それは方向を示します。
だからつまり、きっと、問題はその「方向」で、
この一週間で進もうとしていた「方向」が、
僕の旧知の方向ではなかった。
一週間、「次のコラムがあるぞ」ということで、
自分の知らないことをいろいろ調べようとしていたけれど、
けっきょく、知らないことはうまく書けないのです。
というか、それは単なる「解説」になってしまいがちで、
自分にとって親しみある言葉として発せられない。
だから、要するに、あまりおもしろくない。
もっと大事なことが、あったはずなのに、
という気持ちを、解消することがなかなかできませんでした。
・日曜の夜にレイトショーで『アメリカン・スナイパー』という映画を観ました。
観終わって、とても重たい気分でした。
その『アメリカン・スナイパー』という映画は、
アメリカにおいて賛否両論巻き起こしている映画とのことです。
アメリカのイラク戦争における、ある狙撃手の話で、
なんとこの狙撃手は、160人以上もの敵を殺した、という「伝説の英雄」なのです。
もちろん、ここでいう「敵」というのは、イラク人のことです。
もっというと、主にイラクの「テロリスト」と呼ばれる人たちのことです。
そして「テロリスト」というのは、民兵のような存在だけじゃなく、
ただ普通に暮らしていただけの人、女性や子供も、
武器を手に持って(アメリカを)攻撃しようとすれば「テロリスト」になるのです。
だから、主人公の「英雄」は女性や子供も、
もし攻撃の意志を見せたならば、撃たなければならないのです。
もし撃って女性や子供を殺さなければ、
仲間のアメリカ兵士が殺されてしまうからです。
映画はとても過酷なものでした。
映画が「過酷」というのは、つまり、
観ながらとても「過酷な気分を共有した」ということです。
この主人公の「英雄」、クリス・カイルという名前の人物は、
イラクからアメリカへ帰国しても、
戦場を体験する前のようにおだやかには生活できなくなってしまいます。
ニュースなどでたまに聞く「PTSD」といわれる症状のようです。
そしてクリスは、彼の家族とも心を通わせられなくなってしまうのです。
クリスの「物語」は悲劇的な最期で幕を閉じます。
ある意味でそれは、「物語」として「完成」されたことを意味するように思えました。
問題は、しかし、この「物語」ということだとも思いました。
・クリント・イーストウッドという人が監督したこの作品は、
徹頭徹尾、「アメリカの物語」でした。
「ひとりのアメリカ人」そして「その家族」の「人生」についての映画だったのです。
たぶんここが、賛否の「否」の部分になっていると思うのですが、
つまり、イラクの人の側の物語はまったく描かれていないのです。
僕はこの「描かれなさ」は、「あえて」やっていることなのか、
ということがとても気になるのです。
イーストウッドという監督、あるいは脚本家、製作者たちは、
そういう<非対称性>について、自覚的ではない人たちなのでしょうか。
映画では途中、ムスタファと呼ばれるイラクの側の狙撃手が出てきます。
このムスタファは、主人公のクリスと同じように、
あるいはそれ以上に、正確無比な狙撃をしてくる「強い敵」
(なんとオリンピックの元メダリスト)として登場します。
そしてある面でこのムスタファは、クリスという存在の「イラクバージョン」なのです。
映画では、一瞬ですがムスタファの妻と子供が映るシーンがあります。
それは、ムスタファ(イラク)にも、クリス(アメリカ)と同じように、
守るべきものがあって戦っている
ということを暗示するものだったように思いました。
全編にわたってリアリティが満ちていたこの映画で、
このムスタファという存在だけがなにか「空想的」な余韻をのこします。
とても「意識的」な存在のように思えたからかもしれません。
最初から最期まで、ムスタファはひとこともしゃべりませんでした。
ただ、重要そうな暗示をしめして、消えていきました。
この映画はクリス・カイル本人の自伝的著書を原作にしています。
つまりイーストウッドたちは原作を映画にするにあたって、
物語を相対化させるためにこの(原作にない)ムスタファを登場させたのだと思います。
そこにはいろんな意図があるのだと思います。
・この映画で描かれているような現実、
状況というのは、しかし、他人ごとではまったくないと思うのです。
「アメリカ」や「日本」という国単位で考えるのでなく、
「世界」をまるごとひとつの国として考える、
自分もその一員である、
というような思考が、もしできるとしたら、
どこに何が偏っているのか、
誰が比較的多く大声でしゃべっていて、
誰が比較的常に無言で黙っているのか、
どこに泣いてる人がいて、どこに怒ってる人がいて、
それは、いったいどういう理由なんだろう、ということが、
一国の内側で考えているよりも、もっと広く公正に考えられるはずです。
もちろん、「広い」ことがただいいことだとは限りません。
小さい、ごく身近なところ、僕たちの生活の近辺にも様々な<非対称>があるはずです。
それでも
芸術が欠如すること、
物語が欠如すること、
それは、決定的な「人間性に対する無理解」を生むのではないでしょうか。
中東の現状はそれを証している気がします。
((対称性を、取り戻す方向に息をふきかけるんだ))
((それができなきゃ無意味なんだ))
2015/02/24 9:49 記