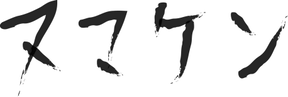2022年 2021年 12月 11月
2月26日(土)
・えーと、普段の自分の活動に集中を戻さないと……。
・“ウクライナの側への相対化”も必要だ……それは僕たち(この「たち」というのは余計だろうか?)がとるべき視点だ。当事国ではないからこその自由な視点が。
・饒舌になれない。自分の言葉への抵抗、懐疑……。
・目が痛い。そうか? そうか……。そうだろう。
・「被害者意識」は暴走を促す。戦争を止める? そもそも「戦争を防ぐ」には?
・ウクライナ人が「助けてくれ」と求めているとき、その求めに“応じていない”と自覚するとき……。
・……考えなきゃいけない、こと、は、善悪二元論、ではなく、単純化される力動から距離をとり、自分の……複雑な作動を内在させた、考え方、捉え方を見つけること。それは、図式的な属性を離れる……いや、単に“図式を複雑化する”だけかもしれないが。
・「政治的に正しい語り口」が規定されていく。「キエフ」は「キーウ」になった。プーチンに親和的な語りは批判され、退けられる。そうか……では、そこに限界線がひかれ、その内側で、ぐるぐると回る「表現」、これを、別の力動にのせないといけない、と感じるのである。
・ラブロフ外相の会見。ウクライナへの批判……BBCの同時通訳……スマートフォンと同期、非同期。情報の流通と……流通しなさ。
・バイデン会見は……。そのショックさ……その根拠。
・なんらかの「フリ」をする。この文章もそうかもしれない。SNSで情報がまわる。SNSで「フリ」をするポーズが加速する。いっさい無視した日常への強度、もある。世界情勢を無視する勇気を自己に讃えた強烈な主体は、また別の上空の限界にぶちあたる……未来を予知する。僕は。しかし、まあ、具体的に、情勢だ。
・「プロパガンダ」というそれっぽい言葉が、内省する動きを阻止する。物語は。相手に口実を与える? 日本にできることのなさ、わたしにできることのなさ……「すべき」は、これから、再生産するもの/しないものを切り分ける。そうだ。
・ウクライナ人を蹂躙するロシア……ロシア人を踏みつけるウクライナ……「目撃」しないのにするディスプレイ。それから共感。ウクライナの「100人の天使たち」。英雄。「大統領は命がけだ」「人々も最後まで戦う」。火炎瓶、銃、抵抗。
・なんでそうなってるんだ?
■
・僕たちは日本人ですね。こないだいった千葉の護国神社。特攻隊の像が立っていたな。あれは……。
・英雄と、それを見る僕。
・“ウクライナの側への相対化”も必要だ……それは僕たち(この「たち」というのは余計だろうか?)がとるべき視点だ。当事国ではないからこその自由な視点が。
・饒舌になれない。自分の言葉への抵抗、懐疑……。
・目が痛い。そうか? そうか……。そうだろう。
・「被害者意識」は暴走を促す。戦争を止める? そもそも「戦争を防ぐ」には?
・ウクライナ人が「助けてくれ」と求めているとき、その求めに“応じていない”と自覚するとき……。
・……考えなきゃいけない、こと、は、善悪二元論、ではなく、単純化される力動から距離をとり、自分の……複雑な作動を内在させた、考え方、捉え方を見つけること。それは、図式的な属性を離れる……いや、単に“図式を複雑化する”だけかもしれないが。
・「政治的に正しい語り口」が規定されていく。「キエフ」は「キーウ」になった。プーチンに親和的な語りは批判され、退けられる。そうか……では、そこに限界線がひかれ、その内側で、ぐるぐると回る「表現」、これを、別の力動にのせないといけない、と感じるのである。
・ラブロフ外相の会見。ウクライナへの批判……BBCの同時通訳……スマートフォンと同期、非同期。情報の流通と……流通しなさ。
・バイデン会見は……。そのショックさ……その根拠。
・なんらかの「フリ」をする。この文章もそうかもしれない。SNSで情報がまわる。SNSで「フリ」をするポーズが加速する。いっさい無視した日常への強度、もある。世界情勢を無視する勇気を自己に讃えた強烈な主体は、また別の上空の限界にぶちあたる……未来を予知する。僕は。しかし、まあ、具体的に、情勢だ。
・「プロパガンダ」というそれっぽい言葉が、内省する動きを阻止する。物語は。相手に口実を与える? 日本にできることのなさ、わたしにできることのなさ……「すべき」は、これから、再生産するもの/しないものを切り分ける。そうだ。
・ウクライナ人を蹂躙するロシア……ロシア人を踏みつけるウクライナ……「目撃」しないのにするディスプレイ。それから共感。ウクライナの「100人の天使たち」。英雄。「大統領は命がけだ」「人々も最後まで戦う」。火炎瓶、銃、抵抗。
・なんでそうなってるんだ?
■
・僕たちは日本人ですね。こないだいった千葉の護国神社。特攻隊の像が立っていたな。あれは……。
・英雄と、それを見る僕。
2月25日(金)
・2022年2月24日。ロシア軍がウクライナ領土に侵攻。歴史的な日になった。
・23日は新松戸FIREBIRDでモーレツアタックのリリースツアーにお邪魔しました。対バンもモーレツも、よかった。楽しかったです。モーレツのラスト2曲は懐かしい鉄板ナンバーで、聞けて興奮しましたね。
・いやあ、ほんと、ライブって楽しいですね。うまくいかないときはきついけどね。でも基本、好きなことやって集まってるんで、幸福なことですよ、ほんと。
・こうやって書くのは24日のロシア軍のウクライナ侵攻があってのことで、「コロナ禍も少しずつ落ち着いてきたかな」「これからまた前向きな、コロナ禍以前の活気や熱を取り戻していくフェーズにいくぞ」と思っていた矢先だった。メンタル的にくるし、少なからず混乱している。自分自身、こうした世界情勢の変化に影響を受けやすいタチだが、今回は本当に大変な事態で、日本の戦後の安全保障にとっても大きな転換点になるのだと思う。
・「思う」と言っても、仕方ない。こうした政治的状況のなかで、自分の言葉を書き残すしかない。
・「大騒ぎしすぎ」「自分の生活に関係ない」「こんなときだからこそいつもどおりやろう」など、いろんな立場があり、それぞれ正しいだろうと思う。「戦争反対」もいい。でもとにかく、自分の言葉をつかみたい。それがないと心もとない。
・自分の言葉か……けっきょく、外からの変化に「考えさせられている」だけで、対応的になっているうちにどんどん時代は変わっている。
・さて、日本のSNS(ツイッター)では「戦争反対と言うのはアリかナシか」といった議論が見受けられる。メタ的な議論だ。そうした自意識の問題にひっかかるのは、いかにも日本的で、良いも悪いもないくらいだ。けれど今回、打ちのめされる現実は、まずプーチンのロシアは想定を超える全面的な電撃作戦をしかけた、そしてウクライナ人は命がけで抵抗姿勢を示している、で、NATOやアメリカはけっきょく「派兵しないよ」と言った、この流れだ。「戦争反対」と言っても、立場によって意味が異なる。ロシア人がロシア国内で「戦争反対」と言うのはリスクがあるし、その言明の対象はプーチン政権であることははっきりしている。1000人規模の人々が拘束されているという。ロシア政府から「外国人エージェント」認定されたら言論の自由も失う。ウクライナ人が「戦争反対」と言うときは、第一にプーチンへの非難ではあるだろうが、海外に助けを求めての言明だと思う。僕はそう感じる。では、そのとき、「西側」の僕たちはなにをするだろうか。なにができる? SNSに「戦争反対」とつぶやき、ハッシュタグデモに参加して、それくらいだろうか。ウクライナ人は命がけで戦い、実際に人が死んで、大統領は「我々は孤立無援だ」と語った。僕たち日本人は、安全圏にいて、「戦争反対」とつぶやく……この非対称性はなんだ? では、僕たちは、自国の政府に「自衛隊をウクライナに派遣しろ」と迫るだろうか。それを主張する人や政治勢力はいるか? この無力感をスルーして、自分に正義があるなんて顔は、僕にはできない。そう思ってしまう。
・わからない。そんな議論はどうでもいいかもしれない。「議論どころじゃない」という議論が危機の際にはいちばん力をもったりする。
・“僕たちはウクライナを見捨てている”。この認識をもたざるをえないし、この認識をなきものにして、正しそうなことを言ってもしょうがないという感じがする。
・「こんな議論はどうでもいい」、そうだ。自意識の問題に過ぎないからだ。具体的に、自衛隊は派遣されないわけだし、よしんば派遣されたとしても、“僕は自衛隊員ではない”のだ。つまり“自分が戦うわけではない”のだ。「国際秩序を守るために自衛隊を派遣しろ」という意見があるとしても、それを発することには別種の負荷がかかる。
・この「重さ」をどう受け止めればいいのか。とりあえず目の前の日常に回帰したほうがいい、いい。「手の届く世界を大事にする」ことしかできないから。そうだそうだそうだそうだそうだ……。
・「瞬間的な条件反射で沸騰しているだけだろう」という批判が聞こえる。そうだ、状況が落ち着けば、切迫感もそのうちに収まる。そうやって時間は過ぎる。根本的な解決はない、ない、ない……。
■
エビ問答
A じゃあお前はどうするの?
B いやどうするもこうするも、なにもできんのだが……。
A じゃあ偉そうなこというなや。戦争反対、と言ってるだけの人らとおんなじ立場だろうて。
B はいそうですよ。くそう。なんだってこんな。
A 戦争戦争って、紛争もふくめて世界中でいつでも起こってることでしょう。なんで今回だけ例外的に反応するのかな。いままでの他の紛争や戦争はどうだってよかった、ってことでしょうか。
B そういうことじゃない。でもメタレベルでそう問われるのは仕方ない。その自覚はもちたい。だが、今回は意味合いが大きい。ヨーロッパでこれだけ大規模な侵略が起こったということだろう……いや、僕にはなにもわからない……が、国内の議論も転換していくことは間違いないだろうからな。
A 個人的に大事だと思うことをするしかないだろう? いままでと変わらない。考えたってしょうがない。
B 遅れていってしまうよ。未来のことを想像しよう。暗いよ。どうしようもなくなってきた。気分が悪い。なんだろう。急速に世界は悪くなっている……いや、懸念を広くしても無意味、と言いたいんだろう。そうやってメタ的なことを言いたい連中ばかりいる。それ自体、なにかの欠落を象徴していると思うけれど。
A いいんだ、いいんだ。もうなんでもいいんだ。
2~3日前まで考えていたことがらも、急速に風化していくね。そんな必要ないのに。突風というのは恐ろしい。人の考えを変える。君はいま風にあてられて、気分がぼうっとしているよ。まず冷静になって、できることに集中していくべきだね。
B ああ、自分でもそう思う。この状況でね……。少し深刻になりすぎた。受け止めきれない部分が多い。特にSNSで情報がたくさんとれてしまう。僕が生きる生涯の間における、長期的な歴史の方向性がこれで変わってきた。じゃあ自分はどうするか。抵抗するとしたら、それは一体どのレベルなのか。それを問わないといけない。“ウクライナに別の道はありえたのか”という問いは内側に問いたい。それは日本の過去に同じ問いを発することと通底するかもしれない。
((エラそうに。Bはここで、しったかぶった賢しらな態度をさらしているぞ))
A というと?
B 戦前の日本も、あるいは戦後の日本も「こうではない別の可能性」がありえた。その別の可能性をひらくには、膠着した考え方ではだめだろう。ひらかないといけない。自分の考え、感性を。戦争状態に突入するほど、おそらく考えもかたくなになる。ウクライナ人は「玉砕」しているよ。大統領は彼らに武器を与えて、抗戦を呼びかけている((と、Bは言っているけど、現実にそういうことなのか?))。それはどんな光景だろう。別の可能性……それを考えることはそれ自体、シビアなことだな。彼らを否定できるか? 命がけで立ち向かう彼らのことを批判できるだろうか。こんな安全圏で暮らす僕が。それを考えてしまう。その自覚のもとに向かい合いたい……まあ、心許ないね。第一に、これは長期的な方向性なんだ。コロナ禍もそうだ。瞬間的な沸騰ほど当てにならないものはないからね。
A 君は自分が「瞬間的な条件反射」をしていると思うかい。
B ああ思う。まったく自分をあてにしていない。今回のことが起こる以前から、課題は課題としてある。いまからどう変化するかわからないが、自分自身の成熟度合いが表現にもあらわれるだろう。芸術の無力さというのは確固たるものがあるね。傲慢になっちゃいけないよ。
((つまらないことを言うなあ、こいつは……。話を聞いて、時間を損した気分だ。そんなナルシスティックなこと言ってる場合じゃないんだ。つまんないこと言ってる暇あったら、自分にできうることのために手を動かせってんだ))
・23日は新松戸FIREBIRDでモーレツアタックのリリースツアーにお邪魔しました。対バンもモーレツも、よかった。楽しかったです。モーレツのラスト2曲は懐かしい鉄板ナンバーで、聞けて興奮しましたね。
・いやあ、ほんと、ライブって楽しいですね。うまくいかないときはきついけどね。でも基本、好きなことやって集まってるんで、幸福なことですよ、ほんと。
・こうやって書くのは24日のロシア軍のウクライナ侵攻があってのことで、「コロナ禍も少しずつ落ち着いてきたかな」「これからまた前向きな、コロナ禍以前の活気や熱を取り戻していくフェーズにいくぞ」と思っていた矢先だった。メンタル的にくるし、少なからず混乱している。自分自身、こうした世界情勢の変化に影響を受けやすいタチだが、今回は本当に大変な事態で、日本の戦後の安全保障にとっても大きな転換点になるのだと思う。
・「思う」と言っても、仕方ない。こうした政治的状況のなかで、自分の言葉を書き残すしかない。
・「大騒ぎしすぎ」「自分の生活に関係ない」「こんなときだからこそいつもどおりやろう」など、いろんな立場があり、それぞれ正しいだろうと思う。「戦争反対」もいい。でもとにかく、自分の言葉をつかみたい。それがないと心もとない。
・自分の言葉か……けっきょく、外からの変化に「考えさせられている」だけで、対応的になっているうちにどんどん時代は変わっている。
・さて、日本のSNS(ツイッター)では「戦争反対と言うのはアリかナシか」といった議論が見受けられる。メタ的な議論だ。そうした自意識の問題にひっかかるのは、いかにも日本的で、良いも悪いもないくらいだ。けれど今回、打ちのめされる現実は、まずプーチンのロシアは想定を超える全面的な電撃作戦をしかけた、そしてウクライナ人は命がけで抵抗姿勢を示している、で、NATOやアメリカはけっきょく「派兵しないよ」と言った、この流れだ。「戦争反対」と言っても、立場によって意味が異なる。ロシア人がロシア国内で「戦争反対」と言うのはリスクがあるし、その言明の対象はプーチン政権であることははっきりしている。1000人規模の人々が拘束されているという。ロシア政府から「外国人エージェント」認定されたら言論の自由も失う。ウクライナ人が「戦争反対」と言うときは、第一にプーチンへの非難ではあるだろうが、海外に助けを求めての言明だと思う。僕はそう感じる。では、そのとき、「西側」の僕たちはなにをするだろうか。なにができる? SNSに「戦争反対」とつぶやき、ハッシュタグデモに参加して、それくらいだろうか。ウクライナ人は命がけで戦い、実際に人が死んで、大統領は「我々は孤立無援だ」と語った。僕たち日本人は、安全圏にいて、「戦争反対」とつぶやく……この非対称性はなんだ? では、僕たちは、自国の政府に「自衛隊をウクライナに派遣しろ」と迫るだろうか。それを主張する人や政治勢力はいるか? この無力感をスルーして、自分に正義があるなんて顔は、僕にはできない。そう思ってしまう。
・わからない。そんな議論はどうでもいいかもしれない。「議論どころじゃない」という議論が危機の際にはいちばん力をもったりする。
・“僕たちはウクライナを見捨てている”。この認識をもたざるをえないし、この認識をなきものにして、正しそうなことを言ってもしょうがないという感じがする。
・「こんな議論はどうでもいい」、そうだ。自意識の問題に過ぎないからだ。具体的に、自衛隊は派遣されないわけだし、よしんば派遣されたとしても、“僕は自衛隊員ではない”のだ。つまり“自分が戦うわけではない”のだ。「国際秩序を守るために自衛隊を派遣しろ」という意見があるとしても、それを発することには別種の負荷がかかる。
・この「重さ」をどう受け止めればいいのか。とりあえず目の前の日常に回帰したほうがいい、いい。「手の届く世界を大事にする」ことしかできないから。そうだそうだそうだそうだそうだ……。
・「瞬間的な条件反射で沸騰しているだけだろう」という批判が聞こえる。そうだ、状況が落ち着けば、切迫感もそのうちに収まる。そうやって時間は過ぎる。根本的な解決はない、ない、ない……。
■
エビ問答
A じゃあお前はどうするの?
B いやどうするもこうするも、なにもできんのだが……。
A じゃあ偉そうなこというなや。戦争反対、と言ってるだけの人らとおんなじ立場だろうて。
B はいそうですよ。くそう。なんだってこんな。
A 戦争戦争って、紛争もふくめて世界中でいつでも起こってることでしょう。なんで今回だけ例外的に反応するのかな。いままでの他の紛争や戦争はどうだってよかった、ってことでしょうか。
B そういうことじゃない。でもメタレベルでそう問われるのは仕方ない。その自覚はもちたい。だが、今回は意味合いが大きい。ヨーロッパでこれだけ大規模な侵略が起こったということだろう……いや、僕にはなにもわからない……が、国内の議論も転換していくことは間違いないだろうからな。
A 個人的に大事だと思うことをするしかないだろう? いままでと変わらない。考えたってしょうがない。
B 遅れていってしまうよ。未来のことを想像しよう。暗いよ。どうしようもなくなってきた。気分が悪い。なんだろう。急速に世界は悪くなっている……いや、懸念を広くしても無意味、と言いたいんだろう。そうやってメタ的なことを言いたい連中ばかりいる。それ自体、なにかの欠落を象徴していると思うけれど。
A いいんだ、いいんだ。もうなんでもいいんだ。
2~3日前まで考えていたことがらも、急速に風化していくね。そんな必要ないのに。突風というのは恐ろしい。人の考えを変える。君はいま風にあてられて、気分がぼうっとしているよ。まず冷静になって、できることに集中していくべきだね。
B ああ、自分でもそう思う。この状況でね……。少し深刻になりすぎた。受け止めきれない部分が多い。特にSNSで情報がたくさんとれてしまう。僕が生きる生涯の間における、長期的な歴史の方向性がこれで変わってきた。じゃあ自分はどうするか。抵抗するとしたら、それは一体どのレベルなのか。それを問わないといけない。“ウクライナに別の道はありえたのか”という問いは内側に問いたい。それは日本の過去に同じ問いを発することと通底するかもしれない。
((エラそうに。Bはここで、しったかぶった賢しらな態度をさらしているぞ))
A というと?
B 戦前の日本も、あるいは戦後の日本も「こうではない別の可能性」がありえた。その別の可能性をひらくには、膠着した考え方ではだめだろう。ひらかないといけない。自分の考え、感性を。戦争状態に突入するほど、おそらく考えもかたくなになる。ウクライナ人は「玉砕」しているよ。大統領は彼らに武器を与えて、抗戦を呼びかけている((と、Bは言っているけど、現実にそういうことなのか?))。それはどんな光景だろう。別の可能性……それを考えることはそれ自体、シビアなことだな。彼らを否定できるか? 命がけで立ち向かう彼らのことを批判できるだろうか。こんな安全圏で暮らす僕が。それを考えてしまう。その自覚のもとに向かい合いたい……まあ、心許ないね。第一に、これは長期的な方向性なんだ。コロナ禍もそうだ。瞬間的な沸騰ほど当てにならないものはないからね。
A 君は自分が「瞬間的な条件反射」をしていると思うかい。
B ああ思う。まったく自分をあてにしていない。今回のことが起こる以前から、課題は課題としてある。いまからどう変化するかわからないが、自分自身の成熟度合いが表現にもあらわれるだろう。芸術の無力さというのは確固たるものがあるね。傲慢になっちゃいけないよ。
((つまらないことを言うなあ、こいつは……。話を聞いて、時間を損した気分だ。そんなナルシスティックなこと言ってる場合じゃないんだ。つまんないこと言ってる暇あったら、自分にできうることのために手を動かせってんだ))
2月18日(金)
1
・ぬーん。考えることを、その先に、すすんでいかないとしょうがないわよね。
・14日は新松戸FIREBIRDでライブ、16日は千葉ANGAでライブ。両日ともいい日だった。これの感想を書きたいんだけど、頭がぼわーっとして、なんか別のことを書かなきゃそっちに取りかかれない、みたいな状態になる。これ、ちょっとしたバーンアウト現象(燃え尽き症候群)みたいなものに近いのかもしれない。緊張のあとに弛緩がくる。「あー、どきどきしたけど、なんだかんだ楽しかったな」というあとに、また日常に戻ると同時に、そんな「スポット」にはまってたりもする。で、こういうのをどうしたらいいかって、よくわかんないんだけど、まあなんか書いてみる。そんで、書いてみようとしてもなんかあんま書くのもおもしろくなくって、うろうろしたりするうちに、また次の「やること」がせまってくる。そんな繰り返しってのがある。
・「考える」という発想は、しばしばなにかの批判のための「考える」だったりするのね。そういうときは、批判をたくましくするために「考える」がある。いっぽう、そういう「考える」じゃなくって、感情を「発見する」ために脳のリソースを使うこともできる。仏教がやるヴィパッサナー瞑想とかはそれなんだとおもうけど。要は、「わたしはいまこう思ってる」「右の手の甲がちょっとかゆいな」「あの人なんであんなこと言うんだろう、ってことに不満がある」「つまりあのひとは思い通りにならないから、いやだ。怒りが頭にめらめら」「あしたのことを思うと、準備不足の不安で胸のあたりがきゅっとなるな」とかをいちいち実況中継のように発見していく。それをやってるとだんだん落ち着いてくるよね、感情をみとめてコントロールできる範囲がひろがるよね、という話。
・「書く」ってことは基本「ひとり」でやることなんで、これを誰かが読んでくれる前提だとしても、発想するのは自分ひとりのものなんですね。だからその距離感というか、孤独さというのは保ってないといけない。他人と一心同体みたいになって、コミュニティのなかで自我をなくすほど埋没したり、いい意味で幸福な状態だと、「書くひと」からはとおざかるのかもしれない。いやそうじゃなくって、たぶんそこは両立できて、生きているかぎりは「自分」と「他人」は区別できて、また「一心同体」というのも無理なんだから、必然的に「書くひと」にならざるをえない、そんでその上での「幸福」もあるよね、ともいえる。
・なんの話をしたいのか自分でもよくわかんないけど、「他人と言葉をかわす」には、自分の側に言葉が用意されてないといけない、と感じる。で、なんの話をしたいのか自分でもよくわかんないときは、書いたりしてるうちにだんだんそれがわかってくるもんで、「他人と確固たるコミュニケーションをする」ということに確信をえるには、どうしたらいいんでしょうね。そんな周辺をさぐってるらしいのだな、いま自分は。
・ひとりとひとりが向き合う「対幻想」の世界。そこにはさまざまな「障害」がある。ビジネスにもいえることですね。しらんけど。
2((ひとつの方向性での思索))
🐯
・「自分の考えてることが、他人にうまく通じない」ってところに表現の原点があって、そこからコミュニケーションの試行錯誤がはじまって、うまくいったりいかなかったりするんだけど、じゃあなんで「他人にうまく通じない自分の考え」なんて持つに至ったんだろう。あれ、おれって、変わってるのかな、みたいな。そんなふうに思いますよね。「変わってる」っていうのは、「他人にはうまく通じないその人だけの考え」をたくさん持ってると、「変わったやつ」になってくんだと思うけど。で、それでいいじゃん、というふうに落ち着かせてくしかない。「おれは変わったやつだ」という前提で、「おれは変わったやつなんだけど、こういうふうに思うんだけど。いや、変なこといってるかもしんないけど」っていうふうにしゃべってくしかないわけで。そこで「おれは変わったやつ」を抜かして「みんなこう考えるべき」という一般論でいくと、たいがい失敗する。
・さいきんは「おれって変わったやつでさ」なんてわざわざいうのも鬱陶しいし、「みんなそれぞれ変わったやつだよね」というタテマエだけは強化されたんで、「変わったやつ」は免責されたように一見みえるけど、じつはぜんぜんそんなことなかったりする。むしろ、いまはみんなが「自分が変わったやつだ、という自覚」のほうを免責された時代だ、と考えたほうが正確な気がするな。
・つまり、それは「変わった考え」が受け入れられる余地が減った、ということ。いいかえれば、自分で「自分が変わったやつだ」ということを認めて、自覚して、その上であえて「変わった考え」を口にしていく、という態度が、あんまり見られなくなったな、ということを意味している。
・そう考えれば、いまは「大人になる」「成熟する」ってことが困難で、わかりづらくて、それが奨励されてもいない時代だな、と思うんだけどね。自分が「変わったやつだ」という内省も、その基準もないから、現実のほうが思い通りにならないことにストレートにいら立ってしまう。「世間」て言葉もイヤな言葉なわけだし、もうそんな「世間」めいた共同幻想なんて成立してないでしょ、みたいに思いがちだけどそれも大間違いなんだなと。こんなにみんながバラバラで、でも同時に「世間」の圧力をかけてくる時代というのは、なんだろうなと思いますね。「バラバラ」だけど「いろいろ」ではない。いや多少は「いろいろ」だけど、そのときの「いろ」には限定が付されていて、ドギツイ原色は「いろいろ」の内から排除されるようになっている。どっかで最初にスクリーニングされてるわけね。
・その「いろいろの幅」が個人的にいちばん気になるところなのよね。マスクをつけない、ってだけで「いろいろ」の内にいれてくんないんだから、これは「いろいろが狭まってる」としかいいようがない。スポーツ選手だと「ワクチン接種しない」だけで大会に参加できないとかね。で、そのくせ「多様性がだいじ」とかいわれても、よくわかんないんですよね。
・そのときの「多様性」というのは、すごく表面的な「属性」を指してるだけだったりする。人種とか国籍とか性別を「いろいろ」にするだけで「得点に加算」しようという運動がもりあがって、それと反対に「個人の内部のいろいろ」には関心が払われなくなって、「40代の男性日本人」というだけでひとつのくくりのなかに入れられたりする。そうなってくると、「変わったやつ」をやってても、「しょせん40代の男性日本人でしょ」という「くくり」のなかで処理されて、いっこうに「個人が世間と摩擦を起こさず」、「40代の男性日本人」という「属性として世間と摩擦を起こす」ようになっていく。
・これは困った。このようにして、たとえば「ミソジニー中年男性」は出来上がっていく。彼らは「変わった個人」になりそこなった「時代のあぶれもの」でもある。ここらへんで、困ってしまうわけですよね。これ以上いくと「トランプ礼賛」ないし「トランプ現象への理解」とかいう話になっていくんだけど、まあわかるひとはわかってる話だし、あんまり凡庸なことしかいえない気がするので、それはいいや。
3
🐭
・うーん。ええと、こういう話をしたいんじゃなかったよな。なんか、文体のせいで話がひっぱられてしまった。
・対幻想の話がしたい。そう、「個人の内部のいろいろ」を「世間」と対峙させるとき、その「抜け道」としてあるのが対幻想の領域だった。伝統的な、その位置づけとして。
・ああ、こういう話も「凡庸」な、たんなる「小理屈」としてしか通用しない、内奥があるんじゃなかったか。
4 いわゆる「エビ問答」
A おいおい、おまえなに書いてんだよ? ってなんだこれ。なんの催し?
B これは「エビ問答」ですね。AとBが交互に会話しますよね。よくありますよね。だからいいと思いますよ。やれば。思う存分ぶんぶんぶぶん。
A いやあ、まいったなああ。そんな対話とかってテンションじゃなかったんだけどね。無意味な会話を書いても無意味だろうってそういう基本的根本的な話なんじゃないでしょうかちがいますか?
B うん。いいと思いますよ、だからそういうので。かまわないんですよ。気にしないでいいですよ。どうせ恥ずかしがってるだけでしょう? 無意味なんだから、って、無意味なのは意味がないってのもね、どうにかこうにか。
A なんだかわかんねえ。
んじゃあ、聞くけど、「対幻想」ってのはよお、男女のあれかい? これかい? ああそうかい?
B まあまあ。よくわかんないのはこっちもですよ。とりあえず落ち着いて、ええと、「対幻想」というのは「一人の個人と一人の個人とのあいだで起こる幻想領域」のことをいいます。まあ、一対の男女のあいだに起こるお互いのイメージとか、想いとか、そういうのですかね。ただべつに「男女」にかぎらなくて、同性同士でもいいわけです。「一人と一人のあいだに起こる幻想領域」が対幻想です。
A おおっと、むっずかしいねえ! ちょっと勘弁してくれよ。もういやだよぉおれこういう話。ついてけねえよお。
B いやいや、ちょっと戯画化しすぎじゃないですか? なんのノリですかね。もっと内容に入っていきましょうよ。
人間の観念の領域は三つにわかれていて、それぞれ「自己幻想」「対幻想」「共同幻想」とよばれます。んで、いま問題の対幻想。これについて考えたい。問題は、対幻想は個人や社会にとってどのような影響をもたらすか、といったところでしょうか。
A んーだからさあ、ちんぷんかんぷんなわけだけどさあ、とにかく男女の恋愛でも友だちとの友情でも、あるいは家族との関係でも、そりゃもちろん一人の個人にとっては大きな影響をおよぼすだろうよ。そんなん当たり前で、でもそれが社会となんの関係があんのよ? この話こういう方向性でオーケー?
B いいと思います。
対幻想と「共同幻想」……つまり「社会」とがどういう関係にあるか。これはとっても深い問題なので、ぼくなんかが安易に語れないのですが、たとえば「国家」は共同幻想ですが、「家族」もそれを集団と考えれば共同幻想なわけです。で、その「家族」を個々に見れば対幻想になります。つまり、「母」や「父」や「兄弟」とのそれぞれの関係、と分割してとらえればそれは対幻想の領域です。誰しもが、家族との関係で多かれ少なかれ不全感を抱いたり、ひとによっては不幸の原因をそこに見たりしますね。「家族との対幻想」とは個人にとっては決定的な影響をもたらすといえます。
A ふん。まあそうかもね。そういうもんだよね人間って。いろいろあるよねほんと。おれも大変だよ……ってそれはいいんだけどさ。で、それと「共同幻想」「社会」ってのはどういう関係があんのさ。
B ぼくもうまく答えられませんが、自分なりの至らない考えを話すなら、そうやって出来上がっている「家族」が集まって「村」や「街」になり、さらには「村」や「街」の集合が「国家」と呼ばれる単位にまで拡張するわけです。だから「国家」の共同幻想をずっとさかのぼれば、それは家族の対幻想に原初があるといえる。そうした考え方をとるとき、国家の首長に対しても「父」や「母」のイメージでとらえることがあると気づく。「偉大な父」「女帝」とかね。
だから、国家の為政者に対してぼくたちが抱いているイメージのプロトタイプは、しばしばその人の家族形態に由来していたりする。そこがまず、重要だと思うんですよね。それから……。
A はいはい。ちょっと話が先にいきすぎだ。理解がおっつかないよ! まあそこまではわかった。要は「お国に対して威勢のいい文句いってるやつは、なんだか不幸そうな顔してんなあ」ってそういうことかい?
B いやいやいや、そんな差別的なことは間違っても言っていないですよ。やめてくださいよ、たのむから……。
A ああ、そう。じゃあそれは取り消すわ。
B そんな単純化してとらえられると困るんですけどね。まあいいです。話を先にすすめると、だから「対幻想」というのがなんにつけてもとっても重要だ、ってことを言いたいんです。そうした問題意識から、考えを深めたいわけです。
A うんうん。いいぞ。どんどんいけよ!
B ……はい。
ぼくが思うに、誰か特定の個人に愛情を抱くとして、かならずそこには自分自身の原初の「愛の鋳型」の反映があります。その「愛の鋳型」を焼き付けるのは、多くの場合「家族」、つまり「親」ということになります。
だから、男女の恋愛でも、友だちや知人との友情でも、そこにその人の「愛の鋳型」の不足の埋め合わせや、当てはめが起こると思うんですね。
そうすると、対幻想というのはその人の自己幻想の派生された鏡か、あるいは異物か、いずれにせよ自己自身に深く由来した根拠がそこに立ち現れていると。そうみなす場合、さらにそこには、「相手側」の同様の条件も重なってくるわけですよね。
A ……ん……ん、んああ? おお、ごめんごめん! ちょっと寝落ちしちゃったよー。なんだか最近寝不足でさあ。……って、ごめんよ、怒んなよお。いや、話、おもしろいよ。それで、ええと、「相手側」がどうしたってえ?
B いいですよ。理屈っぽくてつまんないでしょうよ。知ってるんですよ退屈なのは。でもしょうがない。とりあえず話がひと段落するまでやめられないんで、いきますよ。
つまり対幻想というのは、自己幻想と自己幻想の出会いの契機なんですよ。だから対幻想を想定しないかぎり、他人のことなんてわかんないはずなんですよ。自己幻想それ自体も対幻想によって、つまり「愛の鋳型」によって根拠付けられていますから。
A でも、自己幻想は自己幻想としてそのまんまごろっと、医者が遺体を解剖するように分析できるんじゃないの。対幻想というのは独自の第三領域でしょう。補足的なもんじゃないのかね。
B いや対幻想はたしかに独立した幻想領域です。だから、「他人のことがわかる」ためには、かならずしも「対幻想として出会う」必要はないかもしれない。別に見知らぬ他人の自己幻想をあれこれ考えてもいいわけですね。それはそれで、その「他人のことがわかる」ようにはなるかもしれない。
けれどもっと有機的な、対面の、相互に影響し合った特有の関係といいましょうか、対幻想独自の「わかり合いかた」があると思うんです。それをどうにか言語化できないかなと思いあぐねているんですがね……。
いや、今日はこのへんで時間切れでしょうか。
A うん。そうだねえ。ちょっとこのへんで切り上げないとまずいかもな。じゃあ、また今度話そうよ。ゆっくり。まああせんないでさ。
B はい。ありがとうございます。またお話しましょう。それでは、また。
・ぬーん。考えることを、その先に、すすんでいかないとしょうがないわよね。
・14日は新松戸FIREBIRDでライブ、16日は千葉ANGAでライブ。両日ともいい日だった。これの感想を書きたいんだけど、頭がぼわーっとして、なんか別のことを書かなきゃそっちに取りかかれない、みたいな状態になる。これ、ちょっとしたバーンアウト現象(燃え尽き症候群)みたいなものに近いのかもしれない。緊張のあとに弛緩がくる。「あー、どきどきしたけど、なんだかんだ楽しかったな」というあとに、また日常に戻ると同時に、そんな「スポット」にはまってたりもする。で、こういうのをどうしたらいいかって、よくわかんないんだけど、まあなんか書いてみる。そんで、書いてみようとしてもなんかあんま書くのもおもしろくなくって、うろうろしたりするうちに、また次の「やること」がせまってくる。そんな繰り返しってのがある。
・「考える」という発想は、しばしばなにかの批判のための「考える」だったりするのね。そういうときは、批判をたくましくするために「考える」がある。いっぽう、そういう「考える」じゃなくって、感情を「発見する」ために脳のリソースを使うこともできる。仏教がやるヴィパッサナー瞑想とかはそれなんだとおもうけど。要は、「わたしはいまこう思ってる」「右の手の甲がちょっとかゆいな」「あの人なんであんなこと言うんだろう、ってことに不満がある」「つまりあのひとは思い通りにならないから、いやだ。怒りが頭にめらめら」「あしたのことを思うと、準備不足の不安で胸のあたりがきゅっとなるな」とかをいちいち実況中継のように発見していく。それをやってるとだんだん落ち着いてくるよね、感情をみとめてコントロールできる範囲がひろがるよね、という話。
・「書く」ってことは基本「ひとり」でやることなんで、これを誰かが読んでくれる前提だとしても、発想するのは自分ひとりのものなんですね。だからその距離感というか、孤独さというのは保ってないといけない。他人と一心同体みたいになって、コミュニティのなかで自我をなくすほど埋没したり、いい意味で幸福な状態だと、「書くひと」からはとおざかるのかもしれない。いやそうじゃなくって、たぶんそこは両立できて、生きているかぎりは「自分」と「他人」は区別できて、また「一心同体」というのも無理なんだから、必然的に「書くひと」にならざるをえない、そんでその上での「幸福」もあるよね、ともいえる。
・なんの話をしたいのか自分でもよくわかんないけど、「他人と言葉をかわす」には、自分の側に言葉が用意されてないといけない、と感じる。で、なんの話をしたいのか自分でもよくわかんないときは、書いたりしてるうちにだんだんそれがわかってくるもんで、「他人と確固たるコミュニケーションをする」ということに確信をえるには、どうしたらいいんでしょうね。そんな周辺をさぐってるらしいのだな、いま自分は。
・ひとりとひとりが向き合う「対幻想」の世界。そこにはさまざまな「障害」がある。ビジネスにもいえることですね。しらんけど。
2((ひとつの方向性での思索))
🐯
・「自分の考えてることが、他人にうまく通じない」ってところに表現の原点があって、そこからコミュニケーションの試行錯誤がはじまって、うまくいったりいかなかったりするんだけど、じゃあなんで「他人にうまく通じない自分の考え」なんて持つに至ったんだろう。あれ、おれって、変わってるのかな、みたいな。そんなふうに思いますよね。「変わってる」っていうのは、「他人にはうまく通じないその人だけの考え」をたくさん持ってると、「変わったやつ」になってくんだと思うけど。で、それでいいじゃん、というふうに落ち着かせてくしかない。「おれは変わったやつだ」という前提で、「おれは変わったやつなんだけど、こういうふうに思うんだけど。いや、変なこといってるかもしんないけど」っていうふうにしゃべってくしかないわけで。そこで「おれは変わったやつ」を抜かして「みんなこう考えるべき」という一般論でいくと、たいがい失敗する。
・さいきんは「おれって変わったやつでさ」なんてわざわざいうのも鬱陶しいし、「みんなそれぞれ変わったやつだよね」というタテマエだけは強化されたんで、「変わったやつ」は免責されたように一見みえるけど、じつはぜんぜんそんなことなかったりする。むしろ、いまはみんなが「自分が変わったやつだ、という自覚」のほうを免責された時代だ、と考えたほうが正確な気がするな。
・つまり、それは「変わった考え」が受け入れられる余地が減った、ということ。いいかえれば、自分で「自分が変わったやつだ」ということを認めて、自覚して、その上であえて「変わった考え」を口にしていく、という態度が、あんまり見られなくなったな、ということを意味している。
・そう考えれば、いまは「大人になる」「成熟する」ってことが困難で、わかりづらくて、それが奨励されてもいない時代だな、と思うんだけどね。自分が「変わったやつだ」という内省も、その基準もないから、現実のほうが思い通りにならないことにストレートにいら立ってしまう。「世間」て言葉もイヤな言葉なわけだし、もうそんな「世間」めいた共同幻想なんて成立してないでしょ、みたいに思いがちだけどそれも大間違いなんだなと。こんなにみんながバラバラで、でも同時に「世間」の圧力をかけてくる時代というのは、なんだろうなと思いますね。「バラバラ」だけど「いろいろ」ではない。いや多少は「いろいろ」だけど、そのときの「いろ」には限定が付されていて、ドギツイ原色は「いろいろ」の内から排除されるようになっている。どっかで最初にスクリーニングされてるわけね。
・その「いろいろの幅」が個人的にいちばん気になるところなのよね。マスクをつけない、ってだけで「いろいろ」の内にいれてくんないんだから、これは「いろいろが狭まってる」としかいいようがない。スポーツ選手だと「ワクチン接種しない」だけで大会に参加できないとかね。で、そのくせ「多様性がだいじ」とかいわれても、よくわかんないんですよね。
・そのときの「多様性」というのは、すごく表面的な「属性」を指してるだけだったりする。人種とか国籍とか性別を「いろいろ」にするだけで「得点に加算」しようという運動がもりあがって、それと反対に「個人の内部のいろいろ」には関心が払われなくなって、「40代の男性日本人」というだけでひとつのくくりのなかに入れられたりする。そうなってくると、「変わったやつ」をやってても、「しょせん40代の男性日本人でしょ」という「くくり」のなかで処理されて、いっこうに「個人が世間と摩擦を起こさず」、「40代の男性日本人」という「属性として世間と摩擦を起こす」ようになっていく。
・これは困った。このようにして、たとえば「ミソジニー中年男性」は出来上がっていく。彼らは「変わった個人」になりそこなった「時代のあぶれもの」でもある。ここらへんで、困ってしまうわけですよね。これ以上いくと「トランプ礼賛」ないし「トランプ現象への理解」とかいう話になっていくんだけど、まあわかるひとはわかってる話だし、あんまり凡庸なことしかいえない気がするので、それはいいや。
3
🐭
・うーん。ええと、こういう話をしたいんじゃなかったよな。なんか、文体のせいで話がひっぱられてしまった。
・対幻想の話がしたい。そう、「個人の内部のいろいろ」を「世間」と対峙させるとき、その「抜け道」としてあるのが対幻想の領域だった。伝統的な、その位置づけとして。
・ああ、こういう話も「凡庸」な、たんなる「小理屈」としてしか通用しない、内奥があるんじゃなかったか。
4 いわゆる「エビ問答」
A おいおい、おまえなに書いてんだよ? ってなんだこれ。なんの催し?
B これは「エビ問答」ですね。AとBが交互に会話しますよね。よくありますよね。だからいいと思いますよ。やれば。思う存分ぶんぶんぶぶん。
A いやあ、まいったなああ。そんな対話とかってテンションじゃなかったんだけどね。無意味な会話を書いても無意味だろうってそういう基本的根本的な話なんじゃないでしょうかちがいますか?
B うん。いいと思いますよ、だからそういうので。かまわないんですよ。気にしないでいいですよ。どうせ恥ずかしがってるだけでしょう? 無意味なんだから、って、無意味なのは意味がないってのもね、どうにかこうにか。
A なんだかわかんねえ。
んじゃあ、聞くけど、「対幻想」ってのはよお、男女のあれかい? これかい? ああそうかい?
B まあまあ。よくわかんないのはこっちもですよ。とりあえず落ち着いて、ええと、「対幻想」というのは「一人の個人と一人の個人とのあいだで起こる幻想領域」のことをいいます。まあ、一対の男女のあいだに起こるお互いのイメージとか、想いとか、そういうのですかね。ただべつに「男女」にかぎらなくて、同性同士でもいいわけです。「一人と一人のあいだに起こる幻想領域」が対幻想です。
A おおっと、むっずかしいねえ! ちょっと勘弁してくれよ。もういやだよぉおれこういう話。ついてけねえよお。
B いやいや、ちょっと戯画化しすぎじゃないですか? なんのノリですかね。もっと内容に入っていきましょうよ。
人間の観念の領域は三つにわかれていて、それぞれ「自己幻想」「対幻想」「共同幻想」とよばれます。んで、いま問題の対幻想。これについて考えたい。問題は、対幻想は個人や社会にとってどのような影響をもたらすか、といったところでしょうか。
A んーだからさあ、ちんぷんかんぷんなわけだけどさあ、とにかく男女の恋愛でも友だちとの友情でも、あるいは家族との関係でも、そりゃもちろん一人の個人にとっては大きな影響をおよぼすだろうよ。そんなん当たり前で、でもそれが社会となんの関係があんのよ? この話こういう方向性でオーケー?
B いいと思います。
対幻想と「共同幻想」……つまり「社会」とがどういう関係にあるか。これはとっても深い問題なので、ぼくなんかが安易に語れないのですが、たとえば「国家」は共同幻想ですが、「家族」もそれを集団と考えれば共同幻想なわけです。で、その「家族」を個々に見れば対幻想になります。つまり、「母」や「父」や「兄弟」とのそれぞれの関係、と分割してとらえればそれは対幻想の領域です。誰しもが、家族との関係で多かれ少なかれ不全感を抱いたり、ひとによっては不幸の原因をそこに見たりしますね。「家族との対幻想」とは個人にとっては決定的な影響をもたらすといえます。
A ふん。まあそうかもね。そういうもんだよね人間って。いろいろあるよねほんと。おれも大変だよ……ってそれはいいんだけどさ。で、それと「共同幻想」「社会」ってのはどういう関係があんのさ。
B ぼくもうまく答えられませんが、自分なりの至らない考えを話すなら、そうやって出来上がっている「家族」が集まって「村」や「街」になり、さらには「村」や「街」の集合が「国家」と呼ばれる単位にまで拡張するわけです。だから「国家」の共同幻想をずっとさかのぼれば、それは家族の対幻想に原初があるといえる。そうした考え方をとるとき、国家の首長に対しても「父」や「母」のイメージでとらえることがあると気づく。「偉大な父」「女帝」とかね。
だから、国家の為政者に対してぼくたちが抱いているイメージのプロトタイプは、しばしばその人の家族形態に由来していたりする。そこがまず、重要だと思うんですよね。それから……。
A はいはい。ちょっと話が先にいきすぎだ。理解がおっつかないよ! まあそこまではわかった。要は「お国に対して威勢のいい文句いってるやつは、なんだか不幸そうな顔してんなあ」ってそういうことかい?
B いやいやいや、そんな差別的なことは間違っても言っていないですよ。やめてくださいよ、たのむから……。
A ああ、そう。じゃあそれは取り消すわ。
B そんな単純化してとらえられると困るんですけどね。まあいいです。話を先にすすめると、だから「対幻想」というのがなんにつけてもとっても重要だ、ってことを言いたいんです。そうした問題意識から、考えを深めたいわけです。
A うんうん。いいぞ。どんどんいけよ!
B ……はい。
ぼくが思うに、誰か特定の個人に愛情を抱くとして、かならずそこには自分自身の原初の「愛の鋳型」の反映があります。その「愛の鋳型」を焼き付けるのは、多くの場合「家族」、つまり「親」ということになります。
だから、男女の恋愛でも、友だちや知人との友情でも、そこにその人の「愛の鋳型」の不足の埋め合わせや、当てはめが起こると思うんですね。
そうすると、対幻想というのはその人の自己幻想の派生された鏡か、あるいは異物か、いずれにせよ自己自身に深く由来した根拠がそこに立ち現れていると。そうみなす場合、さらにそこには、「相手側」の同様の条件も重なってくるわけですよね。
A ……ん……ん、んああ? おお、ごめんごめん! ちょっと寝落ちしちゃったよー。なんだか最近寝不足でさあ。……って、ごめんよ、怒んなよお。いや、話、おもしろいよ。それで、ええと、「相手側」がどうしたってえ?
B いいですよ。理屈っぽくてつまんないでしょうよ。知ってるんですよ退屈なのは。でもしょうがない。とりあえず話がひと段落するまでやめられないんで、いきますよ。
つまり対幻想というのは、自己幻想と自己幻想の出会いの契機なんですよ。だから対幻想を想定しないかぎり、他人のことなんてわかんないはずなんですよ。自己幻想それ自体も対幻想によって、つまり「愛の鋳型」によって根拠付けられていますから。
A でも、自己幻想は自己幻想としてそのまんまごろっと、医者が遺体を解剖するように分析できるんじゃないの。対幻想というのは独自の第三領域でしょう。補足的なもんじゃないのかね。
B いや対幻想はたしかに独立した幻想領域です。だから、「他人のことがわかる」ためには、かならずしも「対幻想として出会う」必要はないかもしれない。別に見知らぬ他人の自己幻想をあれこれ考えてもいいわけですね。それはそれで、その「他人のことがわかる」ようにはなるかもしれない。
けれどもっと有機的な、対面の、相互に影響し合った特有の関係といいましょうか、対幻想独自の「わかり合いかた」があると思うんです。それをどうにか言語化できないかなと思いあぐねているんですがね……。
いや、今日はこのへんで時間切れでしょうか。
A うん。そうだねえ。ちょっとこのへんで切り上げないとまずいかもな。じゃあ、また今度話そうよ。ゆっくり。まああせんないでさ。
B はい。ありがとうございます。またお話しましょう。それでは、また。
2月12日(土)
・コロナ禍。入国制限を早く緩和してほしい。オミクロン株の行動制限も緩和してほしいし、まん延防止措置も切り上げてほしい。
・このへん、折に触れて言っとかないと口ごもるようになってしまう。態度を表明していくのは、瞬発力や耐性を保つために必要なことだろうと感じている。
・つれづれと考えていることをつづる。高齢者と若者の対立、みたいな図式。オミクロンは風邪かどうか、という二項対立。こうしたシンプルな図式に回収されがちで、これがけっこう危ういように思う。それやっても水かけ論に終始。おおいにやればいいとも思うが、別の見立てが提示され脱構築されていく回路がもっと必要なはずで、Twitterではそれが見えづらい。
・若者の犠牲、ないししわ寄せはあからさまで、これは後まで禍根を残しそうになってしまった。修学旅行のキャンセルとか、どう考えても安易にやりすぎだろう。「教育」というものが大人の都合で勝手に変質させられてしまったようだ。
・問題は、こうした事象がどこから発しているか。政治は責任をとらなくなっている。岸田政権は政治的な責任主体として最悪の部類に見える。なのに支持率は高い。既存の左派勢力・反体制側の批判力がおよばない。彼らはわかりやすい「巨悪」をでっちあげて叩く快楽に身をやつしている(ように見える)。外国人留学生や鎖国の問題は、もっと騒がれるべきじゃないのだろうか、とも思う。
・しかしそんなこと書いても「じゃあお前が騒げよ」という話で、ここで矛先は反転し、自分に向かわなくてはならなくなるのだが、そりゃそうだ、という話で、SNSでたまにツイートするくらいが関の山、で自足しているのだった。
・こうして書いたことも、「はい。おっしゃるとおりですね。で?」といわれたら、とくに返す言葉はない。
・「そんなことより、お前はお前の“やるべきこと”をやれよ」と、つねに(誰だかよくわからないひとから)いわれるのだが、そいつがいったい誰だかよくわからないし、やるべきこと、というのも、既定路線を疑えば未規定になる。それだから、脱構築するのは自分自身の観念形態だったりする。こうして書くとき、書く矛先が、自己破壊を是とするならば、そうなる。そうならなければ、じっさいつまらない。つまらないことを「いやあけっこうおもしろいですねえ。仲良くしてください」とかいってみだりに肯定しすぎていなかっただろうか。いや肯定はいいのかもしれない。ただその先も肯定しなければならない。「その先」を無意識に否定するがあまり、手前のところでいつまでも内閉しているんじゃないだろうか。たぶんそうで、だからつまらないのは、たんに自分自身だったりする。
■
・自己言及の度合いを増したい。SNSでライブ告知、このホームページの日記や詩の告知、をする。すると、反応をもとめるきもちが惹起するわけですね。んで、これが、なかなか反応えられない、となると、不安感につながる。SNSの評価経済は、ドーパミンやセロトニンと結びついて、強力な拘束力を発揮する(らしい)。なので、とても強い影響関係があるとおもう。じつは。
・その影響関係を脱臼させていたい、とおもう。願わくば。あらゆる現代の(自己)表現が、SNSを中心に組み替えられ、映画の感想をつぶやくのも別の関数がはいりこんでくる。たとえば映画の感想を「漫画」形式にすれば「反応」を多くもらえるだろう。しかしそのとき、もはや目的は「映画の感想を言語化しつたえる」のではなく、「映画の感想を漫画にしてつぶやく自分への得点」にすりかわる。
・「すりかわる」と書いたが、その過程が無自覚に進行することに危うさをおぼえる。自覚的ならば、まだいい。でもかならずネタはベタになる。「他人の物語」と「自分の物語」は混同されたまま、分離されず、人間本来の成熟が疎外されるはめになる。
■
・さて。ここから目指したいのは「SNSから距離をとろう」というようなおあつらえ向きの態度ではなく、むしろ脱構築、からの再編成、といったものにちかい。具体的にどういうものなのかは、まだよくわからない。でももっとダイナミクスをひろげ、知らずしらずに切り捨ててしまった自己言及の鬱陶しさや、現実へのあきらめから失った過去の夢を復活させたりしたい。
・その際、直接話法より間接話法が選択されるべきかもしれない。つまり勝手にひとりごとをいいつづけているほうがよい、と。なにも水脈がないところで、でっかく呼びかけてもなんの波紋も起こらず終わる。
・徐々に口をひらいていく、ということに、あらためて取り組むしかないのだろう。書き言葉と、歌う言葉と、しゃべり言葉と。詩もあれば、こうした散文もあり、歌もあり、と多チャンネルになっていく。そうしていきたい。チャンネルを「合わせる」ということがあるけど、そういう意味で、「合わせる先」があるかないかは大きなちがいだ。「合わせる先」が見つからなければ、路頭に迷って、ひたすら自分を持て余すのみだ。そう、ほとんど見つけがたい、そんな「受信者」がいなければ、実現不可能なことをやろうとしてきたのかもしれない。
■
現実とふれあう?
・文章を書く。読んでくれる人がいるかいないか想像する。宛て先をもたない文章の群れ。歌を歌うときは、その場に人がいるのが前提なのだから、文章とはずいぶん状況がちがう。ライブハウスで歌を歌えば誰か聞いてくれる。インターネットに文章を書いても、宛て名のない手紙とおなじだった。
・だめだ。ねむたい。ねむたい。そんなとき、風邪ひいたとき、頭がほてったとき、いつもより無意識に、よくわからないことを、かく。かける、というのは、なんだろう。なにをかくんだろう。
・言及できない、けっして、できない、ものがある。というか、「言及できないっしょ」と、かってにじぶんで、線をひいてるものが、ある。それは「わきまえる」、それは「マナーをまもる」なのだ。
・そんな、ものが、たくさんあって、この現実を「凍らせる」ことばを、ずっと、安心安全に、封印する。その封印を解くためのカギが、詩だったり、歌だったり、そうそう、ロック、だったりしたんじゃなかったっけ。
・そうだったっけ。どうだっけ。わからない。たぶんわすれた。げんじつ、にふれるための、イヤフォンが、せかい、につうじるための、ちかどう。
■
・あまい。あまりに、あますぎる。ライブハウス、を特権化する。ノルマ、に関するツイートが、ひさしぶりに、SNSで話題になっていた。もう、あんまり、議論になることもないのだ、と、すかすかすかと、すかされる、肩が、つーっと、素通りする。
・どうにかして、回復したいので、復活したいので、ぜんたいせい、ぜんたいじかん、ぜんたいのわたくし、ぜんたいが、いったいぜんたいが、どこかって、とうほくにいって、くさむらにすわって、よあかりにいきをひそめて、みた、みんなといっしょに、おなじものをみた、そのけいけんが、ぜんたいで、もうとおくで、へだてて、かいふくしない、しない、しないのは、さびしくて、いやだ、だった、いやなのに、いやじゃないふりして、へいきってかおをして、たってた、そうして、みおろしてた、みおろして、めがあわなかった、あわない、めを、ちがうものみてるから、まじわらない、しらない、かんけいない
■
・ぼくたちはけっこう群れなので、自分の固有性と(つまりさみしさと)複数性(つまりおおぜいのいち員)と、どっちつかずで、その二重性で、いつもよろしくやっていきたい主体です。死んだともだちの追悼。死んだともだちは、ぼく(たち)。そう言うことができる。でもそう言ってしまったら、すぐ失ってしまう。ぼくは、死んだともだちだ、と言ってしまえば、その瞬間に、分別をこえる仕草とともに、それはすぐさま陳腐化してしまう。
・死んだ。死んだ。死んだひとを、うまくとりあつかうことができない。だから「死んだ」と発話すると、すぐに、現実ときりはなされた、文学的な、高尚な、思想的で抽象的な次元に、ぼくたちの理解は、すっとんで、なんだか手につかめるものがよく、わからなくなってしまう。
・「死」というものは、もう、「不死」であるかのように、ただよいつづけている。SNSでは、死んだともだちは、いまでも「生き」つづけていて、botらしきプログラムを自動生産している。
・SNSには、墓がない。墓がないから、死者は、埋められ、追悼されることができない。ぼくたちが長いあいだ培ってきた、死者への儀礼も、いまのこの現実においては、うまく機能しない。
■
・そうだ。ししゃ。シシャ。そんなことを、考えている。でも……その「かんがえ」もどこか、おあつらえ向きであるかのように、かんじられた。ぼくは、ほんとうは、どう思っているだろう? どこか、ぼくの、「ぼく」とずれて、言葉が、それ用の自律をもって、発せられて、獲得してくるものが、ぼくに回帰すると、これは、うまくマッチしない、余剰をのこすしか、なくて?
・ぼくは、ほんとうは、つまり、だから、「ぼくが死んだらどうなるんだろう」ということを、考えている。その考えが、その寂寥感がさきにあって、それから、他者の死を、考えているんじゃなかろうか。そうだ、そのとおりだ、とおもう。
・ぼくは、ぼくが死んだあと、この「ぼく」という記憶や、その存在や、ぼくがなしてきたすべての行為が、どこにいってしまうんだろう、と、そのことが、不安で、それを定着させる、現実の諸作動が、「きちんと作動してくれないとこまる」と、こう感じているんだ。
■
・死者のことを考えてくれない。だれも。死んだ人間は、不要不急の、役に立たない、なんの価値ももたない、意味のない、存在しないものにすぎない。それは、「データ」にすぎない。ただ、そこにいた、そこに生きていた、という、「データ」だけは、そのままごろっと、残るようになった、といえる。でも、それは、けっして、生きていない。それは、けっして、死んでもいないのだ。
■
・さて。死者を鎮魂することなしに、文明は、前進できないのだ。文化なんてものは、死者をシカトして、成り立つはずがないものなのだ。そのことが、わからない社会ならば、こっちのほうからその社会を、「わからない」と言ったほうがいい。なぜならば、死者がいなければ、死者がのこしたものがなければ、この「ぼく」も、ぼく「たち」も、はじめから存在することができなかったのだから。
・鎮魂とは、死者がのこしたものを、生者がうけつぐための儀礼だろうか。どう、どうしたら、いいんだろう。もうそのことも、よくわからなくなっている。よくわからない。どうしたらいいのか。でも、近づいていくことは、できる。だから、そうやって、そうしていくしかないんだ。わからなくても、やっていかなくちゃならないんだ。
・このへん、折に触れて言っとかないと口ごもるようになってしまう。態度を表明していくのは、瞬発力や耐性を保つために必要なことだろうと感じている。
・つれづれと考えていることをつづる。高齢者と若者の対立、みたいな図式。オミクロンは風邪かどうか、という二項対立。こうしたシンプルな図式に回収されがちで、これがけっこう危ういように思う。それやっても水かけ論に終始。おおいにやればいいとも思うが、別の見立てが提示され脱構築されていく回路がもっと必要なはずで、Twitterではそれが見えづらい。
・若者の犠牲、ないししわ寄せはあからさまで、これは後まで禍根を残しそうになってしまった。修学旅行のキャンセルとか、どう考えても安易にやりすぎだろう。「教育」というものが大人の都合で勝手に変質させられてしまったようだ。
・問題は、こうした事象がどこから発しているか。政治は責任をとらなくなっている。岸田政権は政治的な責任主体として最悪の部類に見える。なのに支持率は高い。既存の左派勢力・反体制側の批判力がおよばない。彼らはわかりやすい「巨悪」をでっちあげて叩く快楽に身をやつしている(ように見える)。外国人留学生や鎖国の問題は、もっと騒がれるべきじゃないのだろうか、とも思う。
・しかしそんなこと書いても「じゃあお前が騒げよ」という話で、ここで矛先は反転し、自分に向かわなくてはならなくなるのだが、そりゃそうだ、という話で、SNSでたまにツイートするくらいが関の山、で自足しているのだった。
・こうして書いたことも、「はい。おっしゃるとおりですね。で?」といわれたら、とくに返す言葉はない。
・「そんなことより、お前はお前の“やるべきこと”をやれよ」と、つねに(誰だかよくわからないひとから)いわれるのだが、そいつがいったい誰だかよくわからないし、やるべきこと、というのも、既定路線を疑えば未規定になる。それだから、脱構築するのは自分自身の観念形態だったりする。こうして書くとき、書く矛先が、自己破壊を是とするならば、そうなる。そうならなければ、じっさいつまらない。つまらないことを「いやあけっこうおもしろいですねえ。仲良くしてください」とかいってみだりに肯定しすぎていなかっただろうか。いや肯定はいいのかもしれない。ただその先も肯定しなければならない。「その先」を無意識に否定するがあまり、手前のところでいつまでも内閉しているんじゃないだろうか。たぶんそうで、だからつまらないのは、たんに自分自身だったりする。
■
・自己言及の度合いを増したい。SNSでライブ告知、このホームページの日記や詩の告知、をする。すると、反応をもとめるきもちが惹起するわけですね。んで、これが、なかなか反応えられない、となると、不安感につながる。SNSの評価経済は、ドーパミンやセロトニンと結びついて、強力な拘束力を発揮する(らしい)。なので、とても強い影響関係があるとおもう。じつは。
・その影響関係を脱臼させていたい、とおもう。願わくば。あらゆる現代の(自己)表現が、SNSを中心に組み替えられ、映画の感想をつぶやくのも別の関数がはいりこんでくる。たとえば映画の感想を「漫画」形式にすれば「反応」を多くもらえるだろう。しかしそのとき、もはや目的は「映画の感想を言語化しつたえる」のではなく、「映画の感想を漫画にしてつぶやく自分への得点」にすりかわる。
・「すりかわる」と書いたが、その過程が無自覚に進行することに危うさをおぼえる。自覚的ならば、まだいい。でもかならずネタはベタになる。「他人の物語」と「自分の物語」は混同されたまま、分離されず、人間本来の成熟が疎外されるはめになる。
■
・さて。ここから目指したいのは「SNSから距離をとろう」というようなおあつらえ向きの態度ではなく、むしろ脱構築、からの再編成、といったものにちかい。具体的にどういうものなのかは、まだよくわからない。でももっとダイナミクスをひろげ、知らずしらずに切り捨ててしまった自己言及の鬱陶しさや、現実へのあきらめから失った過去の夢を復活させたりしたい。
・その際、直接話法より間接話法が選択されるべきかもしれない。つまり勝手にひとりごとをいいつづけているほうがよい、と。なにも水脈がないところで、でっかく呼びかけてもなんの波紋も起こらず終わる。
・徐々に口をひらいていく、ということに、あらためて取り組むしかないのだろう。書き言葉と、歌う言葉と、しゃべり言葉と。詩もあれば、こうした散文もあり、歌もあり、と多チャンネルになっていく。そうしていきたい。チャンネルを「合わせる」ということがあるけど、そういう意味で、「合わせる先」があるかないかは大きなちがいだ。「合わせる先」が見つからなければ、路頭に迷って、ひたすら自分を持て余すのみだ。そう、ほとんど見つけがたい、そんな「受信者」がいなければ、実現不可能なことをやろうとしてきたのかもしれない。
■
現実とふれあう?
・文章を書く。読んでくれる人がいるかいないか想像する。宛て先をもたない文章の群れ。歌を歌うときは、その場に人がいるのが前提なのだから、文章とはずいぶん状況がちがう。ライブハウスで歌を歌えば誰か聞いてくれる。インターネットに文章を書いても、宛て名のない手紙とおなじだった。
・だめだ。ねむたい。ねむたい。そんなとき、風邪ひいたとき、頭がほてったとき、いつもより無意識に、よくわからないことを、かく。かける、というのは、なんだろう。なにをかくんだろう。
・言及できない、けっして、できない、ものがある。というか、「言及できないっしょ」と、かってにじぶんで、線をひいてるものが、ある。それは「わきまえる」、それは「マナーをまもる」なのだ。
・そんな、ものが、たくさんあって、この現実を「凍らせる」ことばを、ずっと、安心安全に、封印する。その封印を解くためのカギが、詩だったり、歌だったり、そうそう、ロック、だったりしたんじゃなかったっけ。
・そうだったっけ。どうだっけ。わからない。たぶんわすれた。げんじつ、にふれるための、イヤフォンが、せかい、につうじるための、ちかどう。
■
・あまい。あまりに、あますぎる。ライブハウス、を特権化する。ノルマ、に関するツイートが、ひさしぶりに、SNSで話題になっていた。もう、あんまり、議論になることもないのだ、と、すかすかすかと、すかされる、肩が、つーっと、素通りする。
・どうにかして、回復したいので、復活したいので、ぜんたいせい、ぜんたいじかん、ぜんたいのわたくし、ぜんたいが、いったいぜんたいが、どこかって、とうほくにいって、くさむらにすわって、よあかりにいきをひそめて、みた、みんなといっしょに、おなじものをみた、そのけいけんが、ぜんたいで、もうとおくで、へだてて、かいふくしない、しない、しないのは、さびしくて、いやだ、だった、いやなのに、いやじゃないふりして、へいきってかおをして、たってた、そうして、みおろしてた、みおろして、めがあわなかった、あわない、めを、ちがうものみてるから、まじわらない、しらない、かんけいない
■
・ぼくたちはけっこう群れなので、自分の固有性と(つまりさみしさと)複数性(つまりおおぜいのいち員)と、どっちつかずで、その二重性で、いつもよろしくやっていきたい主体です。死んだともだちの追悼。死んだともだちは、ぼく(たち)。そう言うことができる。でもそう言ってしまったら、すぐ失ってしまう。ぼくは、死んだともだちだ、と言ってしまえば、その瞬間に、分別をこえる仕草とともに、それはすぐさま陳腐化してしまう。
・死んだ。死んだ。死んだひとを、うまくとりあつかうことができない。だから「死んだ」と発話すると、すぐに、現実ときりはなされた、文学的な、高尚な、思想的で抽象的な次元に、ぼくたちの理解は、すっとんで、なんだか手につかめるものがよく、わからなくなってしまう。
・「死」というものは、もう、「不死」であるかのように、ただよいつづけている。SNSでは、死んだともだちは、いまでも「生き」つづけていて、botらしきプログラムを自動生産している。
・SNSには、墓がない。墓がないから、死者は、埋められ、追悼されることができない。ぼくたちが長いあいだ培ってきた、死者への儀礼も、いまのこの現実においては、うまく機能しない。
■
・そうだ。ししゃ。シシャ。そんなことを、考えている。でも……その「かんがえ」もどこか、おあつらえ向きであるかのように、かんじられた。ぼくは、ほんとうは、どう思っているだろう? どこか、ぼくの、「ぼく」とずれて、言葉が、それ用の自律をもって、発せられて、獲得してくるものが、ぼくに回帰すると、これは、うまくマッチしない、余剰をのこすしか、なくて?
・ぼくは、ほんとうは、つまり、だから、「ぼくが死んだらどうなるんだろう」ということを、考えている。その考えが、その寂寥感がさきにあって、それから、他者の死を、考えているんじゃなかろうか。そうだ、そのとおりだ、とおもう。
・ぼくは、ぼくが死んだあと、この「ぼく」という記憶や、その存在や、ぼくがなしてきたすべての行為が、どこにいってしまうんだろう、と、そのことが、不安で、それを定着させる、現実の諸作動が、「きちんと作動してくれないとこまる」と、こう感じているんだ。
■
・死者のことを考えてくれない。だれも。死んだ人間は、不要不急の、役に立たない、なんの価値ももたない、意味のない、存在しないものにすぎない。それは、「データ」にすぎない。ただ、そこにいた、そこに生きていた、という、「データ」だけは、そのままごろっと、残るようになった、といえる。でも、それは、けっして、生きていない。それは、けっして、死んでもいないのだ。
■
・さて。死者を鎮魂することなしに、文明は、前進できないのだ。文化なんてものは、死者をシカトして、成り立つはずがないものなのだ。そのことが、わからない社会ならば、こっちのほうからその社会を、「わからない」と言ったほうがいい。なぜならば、死者がいなければ、死者がのこしたものがなければ、この「ぼく」も、ぼく「たち」も、はじめから存在することができなかったのだから。
・鎮魂とは、死者がのこしたものを、生者がうけつぐための儀礼だろうか。どう、どうしたら、いいんだろう。もうそのことも、よくわからなくなっている。よくわからない。どうしたらいいのか。でも、近づいていくことは、できる。だから、そうやって、そうしていくしかないんだ。わからなくても、やっていかなくちゃならないんだ。
2月3日(木)
1
・ふりかえり。1月31日は新松戸FIREBIRDにて「MUSIC & FILM」だった。映像ライブ。いつも通り自作の映像を携えて演った。まあ、なんとかかたちになった。このところ考えていることをいれこむ。収れんさせる。対バンのRoredaさん、ロス・インゴブレナブレス・デ・ニューマツド(KEN-KOVA&MAYU)、キクチノブヒロ時々オオクボ、MAUDIEさん、みなさんめっちゃ面白くて、たくさん笑ったし刺激も受けた。
・終演後、対バンのコバケンさんが「プロレス」について語ってくれて、ぼくもすこし考えた。プロレス。ショーであること。リアルな喧嘩でやったら即アウトな行動を、プロレスは「あり」にする。その点は他の格闘技とも共通だけれど、プロレスの場合は「場外乱闘」や「凶器使用」といったパフォーマンスがある。「ルールを逸脱すること」もまた、ショーの一部として組み入れられているのだ。
・リアルなナマの喧嘩とは、まるでちがう。プロレス的であること。それは、「安心して傷つけあえること」に通ずる。だから観客にも通用する回路がうまれる。ちょっと以下、野暮は承知で自分なりにまとめてみた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・ふりかえり。1月31日は新松戸FIREBIRDにて「MUSIC & FILM」だった。映像ライブ。いつも通り自作の映像を携えて演った。まあ、なんとかかたちになった。このところ考えていることをいれこむ。収れんさせる。対バンのRoredaさん、ロス・インゴブレナブレス・デ・ニューマツド(KEN-KOVA&MAYU)、キクチノブヒロ時々オオクボ、MAUDIEさん、みなさんめっちゃ面白くて、たくさん笑ったし刺激も受けた。
・終演後、対バンのコバケンさんが「プロレス」について語ってくれて、ぼくもすこし考えた。プロレス。ショーであること。リアルな喧嘩でやったら即アウトな行動を、プロレスは「あり」にする。その点は他の格闘技とも共通だけれど、プロレスの場合は「場外乱闘」や「凶器使用」といったパフォーマンスがある。「ルールを逸脱すること」もまた、ショーの一部として組み入れられているのだ。
・リアルなナマの喧嘩とは、まるでちがう。プロレス的であること。それは、「安心して傷つけあえること」に通ずる。だから観客にも通用する回路がうまれる。ちょっと以下、野暮は承知で自分なりにまとめてみた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【プロレス的とは?】
【プロレス的たるには】
- ベタを自己劇化(表現の次元へ昇華)することでネタ化し、「安心して傷つけあえる環境」を構築すること(≒プロレスの公共性)。
- プロレスは一種のショー。ショーゆえに観客が安心して見ていられる(本気で傷つけあってると心配しないですむ無意識の安心感)(とはいえネタ化がいきすぎるとリアリティを失い陳腐化する)。
- ベタがベタのままだとリアルすぎて笑えなくなる。リアリティショーだとしてもどこかで編集が必要で、完全に未加工のナマの素材を垂れ流しすると観客はひいてしまう。
- プロレスには審判がいる。審判の存在がショーがショーであることのひとつの保証になっている。審判不在だとルール・基準が規定できなくなり、観客はナマの暴力と直接対峙し、結果として負荷が高まり疲れてしまう。その負荷を下げ、多様な表現が流通しうる回路を活かすことで、場全体の表現の自由度・豊かさが拡張・増殖される(価値の相互および自己増殖)。
- 集団と集団で対立構造をつくりだすのも、プロレス的手法。これも100%虚構ではないが、100%リアルでもない。ある意味プロレス的発想をいれこむことで、現実の膠着した人間関係に動きを与えるユーモアになりうる。
- 以上のエンターテイメント性がプロレスの醍醐味。単なる喧嘩とは次元が異なる。つまり「表現するもの」と「表現されるもの」に距離があり、コントロールされている。
【プロレス的たるには】
- ベタをネタにするにはメタがいる(視点の高次化、再帰的で反省的な自意識)。自己批評が抜け落ちていると高度化に失敗しがち。
- 集団と集団の対立構造を演出する際には、構成員同士においてプロレス的発想への理解がいる。自己劇化が壊れマジギレが起こるとプロレス的倫理は破綻し、観客がひくしかない展開におちいる。
- 同時に観客の理解も必要で、プロレス的発想へのリテラシーがないとベタなハラスメントととらえられ、現代社会では容易に規制され不自由になる。
- 当然ながら、理屈を理解することと実際に演じてみるのはまったく別のことで、実演するにはつねに身体性が問われる。なにごとも修練や確固たるイメージが必要。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・みたいな感じだろうか。これがプロレスファンから見て正しいのかわからない。ただ、プロレスにおけるルールのゆるさ、ルールの訂正可能性はけっこういろいろなところのヒントになる気がする。考えてみればコロナ禍以降、こうしたプロレス的なあり方から社会全体がとても遠くにきた感もある。いま、意味があるのかないのかわからないルールにみんなが不満を抱えながら従っているとき、プロレスのような「ていうかそもそもルールなんて虚構なんですよ」みたいなはっちゃけた様式は、けっこう爽快であるようだ。
2
・31日の映像、およびそのストーリー展開には、補足したいこともたくさんあるが、なかなか詳細には書けないこともある。ただ抽象的に言ってみたい。
・まず問題となるのは実存のかたちだ。「誰の実存のかたちよ?」。具体的には、映像の宛先には5つほど重なった層があった。いく人かの個人であり、場であり、家族であり、さらには歴史である。
・と、こう書いてもなにがなんだかさっぱりだろうが、ともかく書くとして、まず個人にはそれぞれ実存の空白地帯のごときものがある。それがなにに由来するのかそれぞれ異なるところの空白地帯。とうぜん、映像をつくり実演するぼくにもある。その、それぞれ空白地帯を負った人間たちが、交差して共通の場をもつにいたる。ライブハウスとは、ぼくにとって、そういう場だった。
・人は、それぞれ個人では空白地帯を負った存在である。しかし交差し、集合となることで個々に固有の空白地帯を補い合うことができる。それは、いうなれば弱さの集合でもある。逆にいえば、弱いから集まるのだ。
・「ぼくにはあなたが必要なんだ」というとき、空白地帯は、空いた椅子の座席のように、その人をまつ。その人がそこに座れば、空白地帯は、たしかに埋まる。そのような、相互にもたれあったような関係は、どこか家族に似ている。
・実存を考えるとき、人間は結局、家族の問題に帰ってくる。家族の問題から出発し、疑似家族をもとめ、そしてまた旅に出るものもいれば、そこに居続けるものもいる。
・実存の空白地帯とは、その人の家族の空白地帯だ。人は、自らがいやおうなしに背負ったものを超えるため、自分の足を使って歩かねばならない。そうすることなしに、どこにも出ていくことができないから。空白地帯は、別の空白地帯をもとめ、重なり、埋まり、不和にせっつかれ、その都度歩き、そうした繰り返しのなかで、やがて自らの空白地帯のかたちを知るにいたる。
・そうして知った自らの空白地帯は、はじめに思っていたよりも、ずっとこじんまりして、あっけないものだった。けれどその深さに、ぼくはぼくのさみしい顔を見る。そのさみしさに、別のさみしさが重なるとき、人は複数になり、やがてまた、あたらしい家族をつくっていく。その家族がつづいていくとき、そこに出来た歴史は、過去にあった歴史と符合し、そうしてまた、過去から未来へのびる歴史的時間にも、空白地帯が存在するのだと発見する。
・個人の空白地帯は集合し、場を成し、家族をつくり、持続し、そこに歴史が生まれ、そうしてつぎに、歴史の空白地帯があらわれる。しかしその最後の空白地帯は、人々のもっとも無意識にくみこまれ、見ようとしなければ見ることのできない位相にある。31日の映像では、千葉市にあるLOOKというライブハウスについてふれた。いまから77年前、1945年6月10日、千葉市は米軍の爆撃機による空襲を受け、いまの富士見にあった千葉女子師範学校はおおきな被害を受けた。教職員や生徒10人が犠牲になった。その千葉女子師範学校は、いまの千葉LOOKとほぼ隣接した敷地にあった。戦後の復興と再開発で千葉市中央部はおおきくかたちを変えたが、もしその日空襲が学校に及ばなかったら、戦後も千葉女子師範学校がその地に残り続けたら、千葉LOOKはそこになかっただろう。そうしてLOOKという千葉でもっとも老舗のライブハウスから生まれた数々のバンドやムーブメントも存在せず、ぼくが体験した思い出も存在しなかっただろう。千葉女子師範学校が空襲を受けたのは、そのなかで航空機の部品を組み立てていたからだ。つまり千葉は、軍都であり、学生も作業に協力する状況だった。だから同年7月7日にはさらに大規模の空襲を受け、市内中央部の約7割が焼失する被害に見舞われた。「戦争するため」の街はそれだから空襲を受け、子どもを教育するための師範学校が被害を受け、その犠牲によって新たになった土地にライブハウスができ、そこに固有の文化が生まれた。戦前には軍の施設を誘致することによって発展した千葉市は、戦後には経済都市として企業を誘致し発展する。ここに付随する歴史の空白地帯を、どれだけ意識できただろうか。この街の「さみしい顔」は、誰に見られ、いつ、どうやって癒されうるだろうか。
・以上、ぼくはこんなことを考えている。それをこうした文章やライブで表現するのは、「きみ」におなじことを考えてほしいからだ。そうして「それはちがう」とか「そうかなあ」とか言ってくれることを、もとめるからだ。そうして、ああだこうだ言いながら、いまより少しでも歩くための道ができたなら、いつかこの街に眠る「さみしい顔」にも、会いにいってあいさつして、そしたらぼくらはずっと昔のとおい家族にも、おなじ交差点でつながることができる、そう思うから。
1月25日(火)
・23日は新松戸FIREBIRDに「MUSIC & ART」をみにいく。2月14日にコラボさせていただくういりおさん(ライブペイント)が出演。ボニクラマンとのコラボは筆を投げての飛沫散布あり、蛍光絵の具のライティングありととってもダイナミック。出来上がったのは一本の樹木のような、植物に似た怪物のような絵。ボニクラマンの音とシンクロしたライブペイント。ぐぐぐっと興奮。ボニクラマン、ノリノリ。ノリがノッてる。ういりおさんの絵はやっぱり目のモチーフが印象的だ。目と目。コラボさせていただくのがめっちゃ楽しみ。
この日は内容盛りだくさんだった。トップの道太郎with大久保真由×PEGGYから笑えた。笑うしかない。落とし所のさらに下をめがけたMC=シモネタ。はっはっは。歌と演奏は高クオリティで道太郎さんと大久保さんのピアノ×シンセの絡みも堪能。キテレツなのかテンガなのか? そして自分の鏡像がみてるのか? やばい世界に入っていた。PEGGYさんの絵は、まさにコーモンで、ワールドを回収なさっていて流石。
→(Yajirushi)×なかがわ寛奈はロック。リフロック。熱い。なかがわさんの絵もグルーヴ。色の上に色が重なってぐぐわーっと。→(Yajirushi)は聞くのが二回目だが、ロックの原点、これかいなとアガる。演奏もライブペイントも三人がグルーヴしておりました。見てる方も、グルーヴ。没入。ふたつのキノコがわわーっとね。表現パワーをいただいた。
大西英雄×ニシモトヒサオは、もう圧巻のドラムとライブペイントと。途中の「交代」もやられた感。やられる快感。ライブですねえ。ふたりとも楽しそう。いいなあ。大西さんのMCもよかった。OPのSEと登場もよかったんだよな。そういうところも勉強になる。ニシモトさんの絵はいつも気持ちいい。大西さんのドラムやばい。
そしてトリは上上Brothers×ツチヤヒトミ。いやあ、素晴らしかったですね。ツチヤさんの絵はいつも描いてくれる。なにを? ぼくの街。わたしの街。最近、散歩しながら街の夜景をよく見るのですが、家々のひとつひとつに人がいる。ツチヤさんの絵は、遠景を描き、ライブハウスの中と外の街をつなげてくれる。上上Brothersは初見だったのですがとっても素敵でした。空間が、歌世界が、音世界が広がり、定着するツチヤさんの絵とともに展開、イベントを見事に終点へと導いてくれた。ストーリー。
この日の出演者も多数参加する2月14日の「MUSIC & ART」も楽しみですよ。がんばるぞい。
・24日は「まめこ作品展」を拝見。二日連続の新松戸。FIREBIRD裏方のまめこちゃん、その成果物を展示。フライヤーはよく見ていたけど、映像の方をがっつり見たのははじめてで、すごくおもしろかった。こうした裏方たちがいてくれるから我々演者も安心して演奏できるのです。感謝の念なのです。この作業の、膨大な時間の、積み重ね。勤務五年かあ。その継続力、持続力によって生きています。ありがとうございます。ほんとうに。映像もフライヤーも、じっくり見てみると、工夫がほどこされている。それが自分などにも伝わってくる。それを味わう。オムレツも美味しかったー。しかしYOSHIOさんの骨折て五年前だったのか。時間の経過が早い。いつも話題のYOSHIOさんは実際いつも話題。そして気合いのはいったフライヤーの気合い。ほくほく。
この日は内容盛りだくさんだった。トップの道太郎with大久保真由×PEGGYから笑えた。笑うしかない。落とし所のさらに下をめがけたMC=シモネタ。はっはっは。歌と演奏は高クオリティで道太郎さんと大久保さんのピアノ×シンセの絡みも堪能。キテレツなのかテンガなのか? そして自分の鏡像がみてるのか? やばい世界に入っていた。PEGGYさんの絵は、まさにコーモンで、ワールドを回収なさっていて流石。
→(Yajirushi)×なかがわ寛奈はロック。リフロック。熱い。なかがわさんの絵もグルーヴ。色の上に色が重なってぐぐわーっと。→(Yajirushi)は聞くのが二回目だが、ロックの原点、これかいなとアガる。演奏もライブペイントも三人がグルーヴしておりました。見てる方も、グルーヴ。没入。ふたつのキノコがわわーっとね。表現パワーをいただいた。
大西英雄×ニシモトヒサオは、もう圧巻のドラムとライブペイントと。途中の「交代」もやられた感。やられる快感。ライブですねえ。ふたりとも楽しそう。いいなあ。大西さんのMCもよかった。OPのSEと登場もよかったんだよな。そういうところも勉強になる。ニシモトさんの絵はいつも気持ちいい。大西さんのドラムやばい。
そしてトリは上上Brothers×ツチヤヒトミ。いやあ、素晴らしかったですね。ツチヤさんの絵はいつも描いてくれる。なにを? ぼくの街。わたしの街。最近、散歩しながら街の夜景をよく見るのですが、家々のひとつひとつに人がいる。ツチヤさんの絵は、遠景を描き、ライブハウスの中と外の街をつなげてくれる。上上Brothersは初見だったのですがとっても素敵でした。空間が、歌世界が、音世界が広がり、定着するツチヤさんの絵とともに展開、イベントを見事に終点へと導いてくれた。ストーリー。
この日の出演者も多数参加する2月14日の「MUSIC & ART」も楽しみですよ。がんばるぞい。
・24日は「まめこ作品展」を拝見。二日連続の新松戸。FIREBIRD裏方のまめこちゃん、その成果物を展示。フライヤーはよく見ていたけど、映像の方をがっつり見たのははじめてで、すごくおもしろかった。こうした裏方たちがいてくれるから我々演者も安心して演奏できるのです。感謝の念なのです。この作業の、膨大な時間の、積み重ね。勤務五年かあ。その継続力、持続力によって生きています。ありがとうございます。ほんとうに。映像もフライヤーも、じっくり見てみると、工夫がほどこされている。それが自分などにも伝わってくる。それを味わう。オムレツも美味しかったー。しかしYOSHIOさんの骨折て五年前だったのか。時間の経過が早い。いつも話題のYOSHIOさんは実際いつも話題。そして気合いのはいったフライヤーの気合い。ほくほく。
1月19日(水)
・越谷(音楽茶屋ごりごりハウス)に久しぶりにいった。koshigaya ASYLUM 2020の中止以来およそ二年ぶり。みんな、久しぶりに会ったがすぐさま地続きの空気、「二年前のつづき」に接続。ありがたかった。見に行ったライブはヨコタイイチロウくんの企画。「はじめてみたいな風のにおい」てことで、ごりごりに初登場する方々がおおく参戦。新鮮な風。たまたま俺もコロナ禍以降来ていなかったので、新鮮さもひとしお。ヨコタくん(彼はぼくと同い年なのだ)のライブもとてもよく、響いた。
・終演後、案の定おそくまで残り、その場でライブが二本きまった。おおう。その前にEASYGOINGSにも顔を出し、知人にあいさつ。元気で元気で。
・終演後、案の定おそくまで残り、その場でライブが二本きまった。おおう。その前にEASYGOINGSにも顔を出し、知人にあいさつ。元気で元気で。
1月14日(金)
・一週間ぶり日記。いそぎ振り返る。1月7日は千葉ANGAで杏仁豆腐とおしるこ太郎のツアーファイナルでした。対バンからの刺激もあって、杏仁も素敵なステージで癒やされた。シャウト中村さんのステージは演劇めいていて、勉強になったしおもしろかったなあ。
・翌8日は新松戸FIREBIRDに津田新風くんのバースデーイベントその2を見に行った。イベント終盤しか見れなかったが、賑わってて雰囲気もよくて楽しかったー「ニューあらし」も際立ってたね!あらしバンドもよかった。
・そんで10日には愛知県豊田市へ。なにしに?豊田市美術館で開催中のホー・ツーニェン『百鬼夜行』を見に行ったのだ!現代アート的なやつね。往復深夜バスでいきました。いやしかし、眠かったーあんましっかり眠れないな深夜バスは!はははー。
・えーと、ホー・ツーニェンやっぱりおもしろかったです。喜楽亭ってとこでやってた別展示『旅館アポリア』も見た。これはあいちトリエンナーレ2019にて拝見したものの再展示。フクちゃんの映像とか、作者の言葉とか、コロナ禍のいまとつながってるようで考えさせられるー。京都学派ってのも考えるとっかかりになるよな。歴史を別角度で見るきっかけ。
・『百鬼夜行』展はアニメがかわいくて。あと虎もよい。陸軍中野学校とか、ああそんなかんじだったんだーと。しかし虎はいいね。かっこいい。てかおれ寅年だし。東南アジアの数少ない共通項、虎。「うしおととら」のとらとか、うる星やつらのラムちゃんとかも一瞬出てきておもしろかったな。
・12日は新松戸FIREBIRDでYOSHIOと遊ぼうフェスティバル。YOSHIOさんと遊んだわー。みんな遊んで、遊ぶって楽しいよねえ。友達になるにはやっぱり遊ばないとだめよねえ。んで友達っていいよねえ。YOSHIOさんと友達になれてんのかなあ?対バンとか、ライブハウスのつながりって、結局そこの場所でしか会わなかったりするけど、そんなつながりが貴重なもんだと思う。でももっと友達になってもいいのかもしんないな。うん。
・その日、終演後に数人と会話。ちょっと気になる(ひっかかる)テーマも出てきたなあ。これは今後自分でこだわるだろう。
・さて、乱雑な書き散らかしっぷりになったけどこのへんで。どうも〜。
・翌8日は新松戸FIREBIRDに津田新風くんのバースデーイベントその2を見に行った。イベント終盤しか見れなかったが、賑わってて雰囲気もよくて楽しかったー「ニューあらし」も際立ってたね!あらしバンドもよかった。
・そんで10日には愛知県豊田市へ。なにしに?豊田市美術館で開催中のホー・ツーニェン『百鬼夜行』を見に行ったのだ!現代アート的なやつね。往復深夜バスでいきました。いやしかし、眠かったーあんましっかり眠れないな深夜バスは!はははー。
・えーと、ホー・ツーニェンやっぱりおもしろかったです。喜楽亭ってとこでやってた別展示『旅館アポリア』も見た。これはあいちトリエンナーレ2019にて拝見したものの再展示。フクちゃんの映像とか、作者の言葉とか、コロナ禍のいまとつながってるようで考えさせられるー。京都学派ってのも考えるとっかかりになるよな。歴史を別角度で見るきっかけ。
・『百鬼夜行』展はアニメがかわいくて。あと虎もよい。陸軍中野学校とか、ああそんなかんじだったんだーと。しかし虎はいいね。かっこいい。てかおれ寅年だし。東南アジアの数少ない共通項、虎。「うしおととら」のとらとか、うる星やつらのラムちゃんとかも一瞬出てきておもしろかったな。
・12日は新松戸FIREBIRDでYOSHIOと遊ぼうフェスティバル。YOSHIOさんと遊んだわー。みんな遊んで、遊ぶって楽しいよねえ。友達になるにはやっぱり遊ばないとだめよねえ。んで友達っていいよねえ。YOSHIOさんと友達になれてんのかなあ?対バンとか、ライブハウスのつながりって、結局そこの場所でしか会わなかったりするけど、そんなつながりが貴重なもんだと思う。でももっと友達になってもいいのかもしんないな。うん。
・その日、終演後に数人と会話。ちょっと気になる(ひっかかる)テーマも出てきたなあ。これは今後自分でこだわるだろう。
・さて、乱雑な書き散らかしっぷりになったけどこのへんで。どうも〜。
1月6日(木)
・前日5日は新松戸FIREBIRDで津田新風(あらし)くんのバースデーイベント。対バンのみなさんの歌の在り処を堪能し、自分のライブ。3曲やる。精神的な反省点もあり。津田くんには吉本隆明『ひきこもれ』をプレゼント。「言葉の本質は沈黙だ」という文言は出てこないが、吉本さんの価値論が知れる。自分の伝えたいものもそこに入ってるように思えて、これを選んだ。28才は30才の節目を近くにして、自分の針路に思うところもおおいだろう。この本を参考に、ぜひぶれないで生きてもらいたい。うんぬん。と、偉そうに先輩感を出してみる。それはともかく、ミュージシャンとしての活動もブッキングも、自分の信じる通りにやっていってもらいたい。よき一年になれ〜。
・新春。そんな俺は右に左にこんがらがっているが、なるほどどおりでこうだぜ、ってなかんじの認識も得られてきた。ちゃんと生きていきたい。もっぱら生きていきたい所存。2022年は、真面目にがんばりたい。この「がんばり」は、他人から見て「がんばってるな」とわかるほどのがんばり方、ってことやね。むむん。
・新春。そんな俺は右に左にこんがらがっているが、なるほどどおりでこうだぜ、ってなかんじの認識も得られてきた。ちゃんと生きていきたい。もっぱら生きていきたい所存。2022年は、真面目にがんばりたい。この「がんばり」は、他人から見て「がんばってるな」とわかるほどのがんばり方、ってことやね。むむん。
1月4日(日)
・お正月。といってもお正月らしいことは何もないんよ。何もない。ほはは。そんなお正月も立派なお正月。何も恥じることはございません。よろしくやっていけば良いじゃて。
・なにかと頭を支配しがちな事案はあるのだが、明日は新松戸FIREBIRDで津田新風くんのバースデー企画がある。それに体を向かわせる。津田!おめでとう! そう、「おめでとう」だ。誕生日だからな。その日に産まれた記念日ってことなんでな。
・書くことでリズムを調整する。日記ってそんなもん。特に、公開日記だと調整力も高まるのだな、不思議と。明日は10組も出るんだな。津田くん焦ってたけど、よくブッキングできたわー。すごい。10組か。みんな、それぞれ、いろんな人が、いろんな背景をもとに歌いますよ。それは、おもしろいよね。俺も自我を溶かしたい。「ああいろんな人いんなー」つって。それぞれの、人の、歌の力、存在感。感じたら、自分も「群れ」になれるというかね。「一員」として存在できそうだ。
・そうじゃなく、一人で悶々としていると、あまりにも「個人」になってしまい、苦しいときがある。そんなことを思う。なんにせよ、明日は津田くんの日なので、お祝いだっちゅうことや。おめでとうのリズム。
・思いつき。群れ、といえば、「歌の群れ」のようなものが、あるのかもしれない。いつぞや聞いたあの歌。あの人の歌ったあの。そのあの人は、いなくなってしまったけど、歌だけは残っている。そんで、人、ってのはそれぞれ唯一・固有のものだけど、群れ、となると、かたまりになるっつうかなあ。
・大勢のなかの孤独。"ああみんな、いろんな人がいろんなこと思って考えているでんなあ"と、気が抜けていく。歌の群れ。歌は、自分の、固有の歌なんだけど、それがたくさん集まって、地層になって、いつしか忘れられて、つまり聞いた人も亡くなって、また新しい群れができていく。そんな流れ。なにか悩みがあっても、"おや、この歌には、いまの自分と同じ悩みが入っているようですよ……"と、共鳴できたら楽になるかもしれない。別に歌でなくても小説でも映画でも漫画でもいい。でも、僕にとっては「歌」になった。それは、単に、いままで出会った人たちが歌っていた歌が、あるからだ。僕はその歌を「聞いた人」だったので、彼ら彼女らの「歌の群れ」を、記憶にとどめているのだ。
・自分を「個人」「ひとり」と考えると煮詰まっていくけど、逆に「群れ」「あつまり」「一員」と考えると、抜けていくこともあるよなと。そうかもしれん。ただ、「一員」となったときに、あまり数値化した数を前面に出しすぎないほうがよかった。SNSはそうなっているから、郵便的不安が巻き起こる。結果、変な力こぶの入ったがんばりが拡散する……そんなふうに言えば言えるので、「次の(そのまた次の?)時代」はまたちがった主体が前面化するんだろうと予想はできる。
・そう。小難しい話をまた書いているけれど、「みんな似たようなことで苦しんでるよ」とわかったほうが気楽なときもあるよね、って話だ。「歌の群れ」つまり「歌のアーカイブ」は、そんな精神を支える地層として、もっとアクセスできるようになれば、手っ取り早く伝達もできる。ただ、サブスクがそれになるかというと、それを陳列する文脈が本来は必要で、サブスクは単一プラットフォームの"大きすぎる"自由競争なのだ。だから、本来は、有限性が必要で、それが「地域」だったりする。そこではじめて、「群れ」は「仲間」「家族」に近づくことになる。
・なにかと頭を支配しがちな事案はあるのだが、明日は新松戸FIREBIRDで津田新風くんのバースデー企画がある。それに体を向かわせる。津田!おめでとう! そう、「おめでとう」だ。誕生日だからな。その日に産まれた記念日ってことなんでな。
・書くことでリズムを調整する。日記ってそんなもん。特に、公開日記だと調整力も高まるのだな、不思議と。明日は10組も出るんだな。津田くん焦ってたけど、よくブッキングできたわー。すごい。10組か。みんな、それぞれ、いろんな人が、いろんな背景をもとに歌いますよ。それは、おもしろいよね。俺も自我を溶かしたい。「ああいろんな人いんなー」つって。それぞれの、人の、歌の力、存在感。感じたら、自分も「群れ」になれるというかね。「一員」として存在できそうだ。
・そうじゃなく、一人で悶々としていると、あまりにも「個人」になってしまい、苦しいときがある。そんなことを思う。なんにせよ、明日は津田くんの日なので、お祝いだっちゅうことや。おめでとうのリズム。
・思いつき。群れ、といえば、「歌の群れ」のようなものが、あるのかもしれない。いつぞや聞いたあの歌。あの人の歌ったあの。そのあの人は、いなくなってしまったけど、歌だけは残っている。そんで、人、ってのはそれぞれ唯一・固有のものだけど、群れ、となると、かたまりになるっつうかなあ。
・大勢のなかの孤独。"ああみんな、いろんな人がいろんなこと思って考えているでんなあ"と、気が抜けていく。歌の群れ。歌は、自分の、固有の歌なんだけど、それがたくさん集まって、地層になって、いつしか忘れられて、つまり聞いた人も亡くなって、また新しい群れができていく。そんな流れ。なにか悩みがあっても、"おや、この歌には、いまの自分と同じ悩みが入っているようですよ……"と、共鳴できたら楽になるかもしれない。別に歌でなくても小説でも映画でも漫画でもいい。でも、僕にとっては「歌」になった。それは、単に、いままで出会った人たちが歌っていた歌が、あるからだ。僕はその歌を「聞いた人」だったので、彼ら彼女らの「歌の群れ」を、記憶にとどめているのだ。
・自分を「個人」「ひとり」と考えると煮詰まっていくけど、逆に「群れ」「あつまり」「一員」と考えると、抜けていくこともあるよなと。そうかもしれん。ただ、「一員」となったときに、あまり数値化した数を前面に出しすぎないほうがよかった。SNSはそうなっているから、郵便的不安が巻き起こる。結果、変な力こぶの入ったがんばりが拡散する……そんなふうに言えば言えるので、「次の(そのまた次の?)時代」はまたちがった主体が前面化するんだろうと予想はできる。
・そう。小難しい話をまた書いているけれど、「みんな似たようなことで苦しんでるよ」とわかったほうが気楽なときもあるよね、って話だ。「歌の群れ」つまり「歌のアーカイブ」は、そんな精神を支える地層として、もっとアクセスできるようになれば、手っ取り早く伝達もできる。ただ、サブスクがそれになるかというと、それを陳列する文脈が本来は必要で、サブスクは単一プラットフォームの"大きすぎる"自由競争なのだ。だから、本来は、有限性が必要で、それが「地域」だったりする。そこではじめて、「群れ」は「仲間」「家族」に近づくことになる。
1月1日(土)
・新年あけましておめでとうございます。2022年となりました。寅年です。いちおうぼく、年男です。
・というわけで、相変わらず徒然とですが、大晦日の新松戸FIREBIRDイベントから振り返っていきたい。FIREBIRDでは二年ぶりのカウントダウンイベント。ひとまず、できてよかった。そのことへの安堵と、お店ががんばってきた矜持と。多少なりとも出演というかたちで関わりをもたせてもらった自分としても、感慨深さがあると同時に、イベントの意味もまた思う。
・コロナ禍。いろいろあったが、その1つの区切りになったんじゃないだろうか。店長のダイゴさんはじめ、みんな明確に言わないけれど、そんな無意識の共有があったような気がした。そんなこと感じたの俺だけかな。でも、年が明けて帰り際、事務所で机に突っ伏して寝てる(珍しい)ダイゴさん見て、なんかほんと、お疲れさまでした!って思ったな。
・出演者は濃厚で、普段対バンしない方々が多く、どんな感じの景色になるかな、と思ってたけど、やっぱりみなさん楽しい巧者ばかり。「芸」を堪能させてもらって、そこにロックもパンクも下ネタもフォルクローレもブギウギもフォークもあって、まことに賑わっておった。トップのガンバリマンコスモスからカウントダウンの道太郎さん、トリのあみへーノさんまで祝祭空間になっておりました。
・俺は“沼田謙二朗with大久保真由”で出演。詩の朗読など、いつもと違う新しい試みもあり、準備していたことが通ずるかな、うまくいくかなと自分の中の不安もあったが、無事に、ちゃんとできてよかった。緊張と興奮入り交じったテンションで危ないヒゲおじさんみたいになってましたが、危なさは危ないまんま着地できてよかった。大久保さんのピアノ、詩、キャラクターのおかげでした。大久保ファンも増えたようでなによりだ。15年ぶりくらいにライブで着た赤いジャケットは瘋癲野朗時代に着ていたものだった。実は、「原点回帰」という隠れたメッセージがそこにあった(かもしれない)。敬愛するYOSHIOさんとはもっと上手にからめるようになりたい。マンマークよりゾーンプレス。その精神と関係性の機微をちゃんとかわしてゴールネットを揺らせるように。みんなでラブ&ピースになりたいですね。
・スタッフのみんなもこういう長丁場の日は大変だ。みんなお疲れ様だ。でも楽しい日になって、熱量があって、いいですよね。振り返れば、コロナ禍いろいろあったなあ……って、まだ油断してる場合でもないけど。緊急事態宣言も時短営業も禁酒も、忘れられない経験になった。2020年の4月ごろからつづいた一連の流れが、「昨年やれなかったイベントが今年やれる」というかたちでもって、区切られた感。その時期含めてお店に来てくれていたお客さんとは、ちょっとした「戦友」みたいな感覚がある。あの、ほとんどの店が閉まっている一回目の緊急事態宣言のなかで、ライブをやった体験。それは、「その場にいた人にしかわからない共通体験」に思えた。さて沼田は"政治的に正しいとはかぎらない"ので、かような時勢も反転して茶化したりするときもあるが、そんな「悪ふざけ」も(もうちょっと)社会にあってもいいよなと思う。この「悪ふざけ」も、思えば原点的なものといえるかもしれない。つってもそんな、いうほど過激なことはやってないけども。
・個人的には2021年は、調子の悪い時期もあったり、それでもFIREBIRDは継続的に声をかけてくれて、店長のダイゴさんも、ブッキングのアラシくんも、とてもありがたかった。やっぱり"ライブする"という機会がなくなると、自分が能動的になることもままならなくなる、とわかり、もう一度集中して後半戦に向き合った。この調子で2022年もがんばりたい。ずっと停滞させていたことも多いが、今年こそはもっとわかりやすく動いていきたいなと思う。
・というわけで「おかげさまで……」の感。まだ書くべきことはいろいろありそうだが、ひとまずこのへんで、新年もよろしくお願いいたします。
・というわけで、相変わらず徒然とですが、大晦日の新松戸FIREBIRDイベントから振り返っていきたい。FIREBIRDでは二年ぶりのカウントダウンイベント。ひとまず、できてよかった。そのことへの安堵と、お店ががんばってきた矜持と。多少なりとも出演というかたちで関わりをもたせてもらった自分としても、感慨深さがあると同時に、イベントの意味もまた思う。
・コロナ禍。いろいろあったが、その1つの区切りになったんじゃないだろうか。店長のダイゴさんはじめ、みんな明確に言わないけれど、そんな無意識の共有があったような気がした。そんなこと感じたの俺だけかな。でも、年が明けて帰り際、事務所で机に突っ伏して寝てる(珍しい)ダイゴさん見て、なんかほんと、お疲れさまでした!って思ったな。
・出演者は濃厚で、普段対バンしない方々が多く、どんな感じの景色になるかな、と思ってたけど、やっぱりみなさん楽しい巧者ばかり。「芸」を堪能させてもらって、そこにロックもパンクも下ネタもフォルクローレもブギウギもフォークもあって、まことに賑わっておった。トップのガンバリマンコスモスからカウントダウンの道太郎さん、トリのあみへーノさんまで祝祭空間になっておりました。
・俺は“沼田謙二朗with大久保真由”で出演。詩の朗読など、いつもと違う新しい試みもあり、準備していたことが通ずるかな、うまくいくかなと自分の中の不安もあったが、無事に、ちゃんとできてよかった。緊張と興奮入り交じったテンションで危ないヒゲおじさんみたいになってましたが、危なさは危ないまんま着地できてよかった。大久保さんのピアノ、詩、キャラクターのおかげでした。大久保ファンも増えたようでなによりだ。15年ぶりくらいにライブで着た赤いジャケットは瘋癲野朗時代に着ていたものだった。実は、「原点回帰」という隠れたメッセージがそこにあった(かもしれない)。敬愛するYOSHIOさんとはもっと上手にからめるようになりたい。マンマークよりゾーンプレス。その精神と関係性の機微をちゃんとかわしてゴールネットを揺らせるように。みんなでラブ&ピースになりたいですね。
・スタッフのみんなもこういう長丁場の日は大変だ。みんなお疲れ様だ。でも楽しい日になって、熱量があって、いいですよね。振り返れば、コロナ禍いろいろあったなあ……って、まだ油断してる場合でもないけど。緊急事態宣言も時短営業も禁酒も、忘れられない経験になった。2020年の4月ごろからつづいた一連の流れが、「昨年やれなかったイベントが今年やれる」というかたちでもって、区切られた感。その時期含めてお店に来てくれていたお客さんとは、ちょっとした「戦友」みたいな感覚がある。あの、ほとんどの店が閉まっている一回目の緊急事態宣言のなかで、ライブをやった体験。それは、「その場にいた人にしかわからない共通体験」に思えた。さて沼田は"政治的に正しいとはかぎらない"ので、かような時勢も反転して茶化したりするときもあるが、そんな「悪ふざけ」も(もうちょっと)社会にあってもいいよなと思う。この「悪ふざけ」も、思えば原点的なものといえるかもしれない。つってもそんな、いうほど過激なことはやってないけども。
・個人的には2021年は、調子の悪い時期もあったり、それでもFIREBIRDは継続的に声をかけてくれて、店長のダイゴさんも、ブッキングのアラシくんも、とてもありがたかった。やっぱり"ライブする"という機会がなくなると、自分が能動的になることもままならなくなる、とわかり、もう一度集中して後半戦に向き合った。この調子で2022年もがんばりたい。ずっと停滞させていたことも多いが、今年こそはもっとわかりやすく動いていきたいなと思う。
・というわけで「おかげさまで……」の感。まだ書くべきことはいろいろありそうだが、ひとまずこのへんで、新年もよろしくお願いいたします。