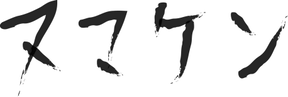|
はじめに
音楽を使って共同体を創出したい。ぼくはそんな夢をどこかに抱いて20代を過ごした。しかし具体的になにをするでもなく、結果からいえばなにもない。ひきこもり気質のぼくが共同体をつくりたい、なんていうのは馬鹿げた夢想のように聞こえるかもしれないが、ひきこもり気質だからこそ、求める共同体に切実になるのだ。 あるいはこういえるかもしれない。ぼくはぼくの生きやすい場所をつくりたい。生きやすい場所をもちたい。音楽を使って、その場所をつくりたい。 「音楽にはなにができるか?」と問うとき、まず第一番目に自分のそういった願望を思い浮かべる。自己表現は自分の存在を他者に承認してもらうことが第一眼目になる。 しかし、ここで問題が生ずる。自分が承認された場所は、他者にとっても承認される場所であるか? いいかえれば、ひきこもっていた自分が場所に入れなかったように、どこかの誰かがその場所に同じように入れなくなってしまう、ということは起こらないのだろうか。(不可逆の階段の非往復性) このとき、自分が異和であった場所の記憶と、自らが親和するにはいかにあるべきか、という課題があらわれる。それにはひとつこう答えたいとおもう。かつての異和を状況によって消去するのではなく、異和ある状況を保ったまま融和できるか、それが根本的な問題なのだと。 優越ゲームとは別のゲームへ みんな誰かに、みとめられたい。承認を集めるために音楽をする。ほとんどの音楽の場は自然な意味で優越ゲームである。実際、ときたまライブの場で「今日はあなたが一番よかったよ」などと口にしあったりする。しかし、そんなせまい場での順位づけをしていて、なんになるだろう。外の世界にはさらなる「一番」がいるに決まっている。むしろ、ぼくたちがすべきなのは優越ゲームではない別のゲームをはじめることではないか。 ぼくはそうおもった。でも、そうできなかった。優越ゲームではない別のゲームなんて、どうやってすればいいのか。よくありがちな、お寒い標語じゃんか。そんなこといっても、やっぱみとめられたいし。せまい世界で、いい気になっていたいのだ。 人間は自然状態では互いに闘争しあうという「リヴァイアサン」のように、ただただ競い合う。優越ゲームじゃない別のゲームをはじめるというのは、なかなか無理のあることなのだ。自然にはそうならない。ぼくとしては、その無理のあることを可能にするなにかがほしかった。 いくつかの「なにか」が頭にはある。それは人間の平等性と本質に関わることがらだ。「沈黙」ということがそのひとつといえる。表現の現場においては「眠っているその人の価値」とでも呼べるものかもしれない。吉本隆明氏の主張したこの概念は、ぼくの価値観にとって基底的な意味をもつものとなった。 あらゆる表現があらわれているところというのは、その結果だ。おおもとにはその人の「沈黙」がある。この「沈黙」というところを見てみれば、実は、人と人は等価である。そしてどんな人でも、しゃべれない人でも、まったく表現ができない人でも、「沈黙」をもっている。 もしかしたら、いいすぎかもしれない。「沈黙」においても個々人の優劣の差は見いだしうるからだ。それは俗にいえば「心の豊かさ」のようなものだ。でも、優越ゲームを考え直す出発点に、この「沈黙」の考えはあるべきだとおもえた。 (ところで、なぜそんなに優越ゲームをいやがるか。じぶんだって、その上にのっかってふるまっているのに。) 沈黙の効用 ある人の沈黙Aとまた別のある人の沈黙Bは等価である。これを表現としてとりだし提示することが芸術であるとする。ある人の沈黙は細部ある表現として提示される。沈黙の領域と世間の領域が交わることで価値の再編成がなされる。ある表現Aとまた別のある表現Bは世間上の価値においてははげしく優劣づけられていた。しかし沈黙Aと沈黙Bは等価である。 表現と沈黙の関係はパラドックスめいている。等価であるはずの沈黙を表現することで、その表現が価値づけられる。すると等価性は消える。等価性を保存しつつ表現するには、行き道だけでなく帰り道が用意されていなくてはならない。(宮沢賢治『マリヴロンと少女』はこの問題を扱っている。) ぼくらはみんなうまくなりたいし、みとめられたい。大概うまくなればみとめられる。それでうれしくなって自足できればそれで十分だ。けれど、自分が認められて、それで満足したとして、その状況はいつまでつづくだろう。いつか終わるかもしれない。また転落するかもしれない。そしてそれ以上に、そもそもはじまりにあった「沈黙の等価性」が、失われていくことに追認しているだけでいいのだろうか。 ぼくはここで「へたくそでもみとめろ」と言いたいのではない。うまいへたを評価の軸にするな、ということではない。表現のいいわるいは厳にある。しかしそれと同時に、根本領域にある沈黙の等価性に自覚的であるべきだといいたいのだ。(世俗価値と沈黙の二層構造≒グローバリズム/スケールフリー/べき乗分布とナショナリズム/スモールワールド/正規分布の二層構造)つまり二項対立ではなく二項並立としてとらえることが正解だ。 この二項並立の世界認識のうえで、いかなる戦略、方法論がありうるか。 二項並立の上で 具体的な戦略が必要だった。いまこの時代においてなにをしていけばいいのか、よくわからなかった。周囲が言う「考える前にやれ」という命題が、だんだんうまく機能しなくもなっていた。 この身動きできない感じは、なんなのか。どうすれば、もっと自由に動けるようになるか。ぼくは、自分に固有の資質と、この時代における表現者の在り方が交わる接点を探したかった。そこに自分の問題解決をはなれて、公共的な意味をもつ在り方があるはずだった。 自分の理由 では、ぼく自身としては、いったい「どこ」に身をうずめたいか、ということだ。それは、自分の時間をどの場所で使い果たすかということとつながっている。 ライブハウスという場所が存在して、その場所が、ぼくにとって重要であるならば、また、さらにもっと重要にしたいのならば、その場所に自分がいなければいけない。その先に、人が人としてもっと自由で平等であり、なおかつ違いを受け入れていられるような、理想に近い人間のつながりのかたちがありうるならば。 ぼくはぼく自身の人生の突破口と重ねたかたちで、この問題を考える。それが有益なるものに、つまりは公益にかなうようにしたい。ぼくにとって生きやすい場所は、ぼく以外の人にとっても生きやすい場所でありうる。しかしそうじゃない場合もありうる。ただ、ぼくとしては、ぼくが生きうる方途を、その最善を探すことに対して、後ろ向きにはなりたくないのだ。 悩んでいても、しょうがなかった。その場にいれば力を発揮できる場所にいたいと願うのは当然のことであり、個人の権利でもある。 社会への目線 自分の理由と、そこから離れたもっと普遍的な理由とのふたつによって、人の行動は出来上がるようにおもう。後者のことを考えたい。ライブハウス、および音楽活動によって、いかなることが可能であるか。いいかえればなぜ、音楽はなければならないのか。そのような問いに大まじめに答えることが必要だ。 音楽という作用、音楽という身体表現は、演者にとっては自己表現たりうる。自己表現というのはなにかというと、自分の中のかたちにならない思いを含めた、ある観念の表現、記憶や風景の表現、恋愛感情や喜怒哀楽の表現など、個人の中のあらゆる感情や思念の表現のことだ。それが、誰か別の他者に対して、自分を離れて作用し、共鳴する。それが音楽のダイナミズムであり魅力である。これは音楽に限らず芸術全般にいえる要素だとおもう。(ここでは、音楽を主にポップソングなどの「歌」を前提にとらえている。しかし歌以外の音楽においてもそれは自己表現といえるとおもう。身体表現であってもエレクトロであってもその人間の取捨選択によって成り立つからだ。) では自己表現を作動させ、観客に共鳴させることによって、いかなることが起こるのか。なぜ、それはなければいけないのか。 中沢新一は芸術のはじまりをラスコーの壁画のような、古代人類の洞窟内における活動に求めた。それは人類の知性にとって革命的な出来事であり、以後、人類は「概念」を手にし、抽象的な思考が可能な存在へと至る。ここに「詩」や「音楽」の原初的な居場所はあるようにおもう。 音楽は、詩よりもさらに古いものかもしれない。人間以外の動物、鳥の一部などにも音楽に近いような声のコミュニケーションが見られる。それは「音楽」といってもいいものかもしれない。 表現とシェルター ぼくたちは、まったくもってハードルを下げ、小さな実現可能な成功を追い求めるべきだ。たとえ小さなスケールであっても、理念だけは無限に拡張しうる。なにかの力がなくては、実際、無力を擁護することもできないのだ。もし表現の場が無力なもののためのシェルターであるときには、そこには最低限の力が注入されなくてはならない。シェルターが外部からの空気遮断機であるならば、遮断する機構が設置されなくてはならない。さて、ではそこで表現者とは、無力なものの擁護者だろうか。それとも無力なものそのものが、表現者なのだろうか。 演者と観客音楽の場を考えるとき、表現する側とそれを見る側、演者と観客という二項が原則としてあるようにおもえる。しかし実際の現場では、演者が観客も兼ねているような場合が多い。たとえば演者が5組いて、観客がそれぞれ1人ついて来てくれれば、観客は5人いることになる。演者が二人組グループ5組で10人だとしたら、観客が5人であったとすると、演者の数の方が観客の数より多いことになる。こうした場合、その場では観客に対して演奏するというよりもむしろ、演者集団に対して演奏するという意識の方が濃くなるのは必然である。実際ぼくがライブする場において、観客が5人でもいれば多い方で、それ以下であることもまったくめずらしくない。 ぼくたちはまずこの現実から向かい合わないといけない。観客がいない。いままでのライブハウスのあり方は、観客がいることを前提として設計されている。観客がいなくなったらライブハウスは成り立たないのだ。 さらにもうひとついえば、いまでは演者も少なくなった。観客がいないということと、演者がいないということは相似関係にあるが、若者がなぜ音楽を志すかということを思い直してみても、異性にモテるだとか、ミュージシャンへの憧れだとかがあったはずで、それは観客がいることによってはじめて成り立つイメージであった。そのイメージが成り立たないならば、演者になりたがる者がいなくなるのは当然である。 アジカン後藤はツイッターにおいて、ファンから「政治を語られると違和感がある」というメッセージを受けた。このやりとりはとても印象的だった。そのファンはどうして違和感を感じるか、自分の言葉では言えなかった。ただ確かにそう感じる、としか。 ここでの後藤のとまどいはどういうものだったか。なぜこのファンは違和感を感じたか。なにか微妙な問題がここには潜んでいて、なおかつ言葉として取り出すのが困難なような気がした。(吉本隆明の転向論のような論理が、なにか適用できないかと考えたりもした) 性愛を歌うロックと、政治を語る後藤の在り方のズレ。そのズレは、彼の存在を全的に享受しようとするファンにとっては、許容できない類いのものだったろうか。ではそこではいったいなにがズレてしまっているのだろうか。 承認としてのロックロックは承認音楽である。歌い手の承認と、聞き手の承認の。私小説が承認文学であるのと同義だ。もちろん、そう言い切れないロックもある。ここで問いたいのは後藤がひきだしたイメージは、聞き手にどういう幻想を用意したかだ。 演者と観客ライブハウスにおいて演者が期待するものと、観客(となるもの)が期待するものとは、かみあっているだろうか。人やバンドによっては疑似恋愛を期待するものもいるし、単に身体的、精神的な高揚感を期待するものもいる。様々なバンドや演者のかたちがある。 僕がここで考えたいのは、まさに、僕自身がこれから音楽活動する際に有効な手立て、方策だ。闇雲に活動し、歌を歌い、曲を作り、練習したりしても、根本的な疑義は晴れない。この疑義が晴れない感覚が、僕の心をにごらせていたようにおもう。疑義を一掃しなければならない。それができるか。 ◆論点出し 論点1 演者と観客の関係性 論点2 ライブハウスのありかた 論点3 時代状況への対応 論点4 ポップミュージックの来し方 論点5 理想的な共同体はなにか。音楽においてそれは構想できるか 論点6 ありうべき音楽のすがた。ありうべき音楽活動のかたち 音楽について この試みは僕のひとつの解答です。歌うことをつづけてきて、それ以前にギタリストとしてやってきて、そもそも音楽にできることがなんなのか、わからなく
なっていました。音楽が信じられなくなっていったときに、「歌うこと」だけじゃなく「聞くこと」も同じように大事だったんだよな、と気づいた。歌うことばかり
考えつづけて、一方通行になっていたのです。 …本音を言えば、僕は売れたいと思えませんでした。自信がないからだ、とずっと思っていました。でも、そういう問題じゃなかったようです。売れた後のイメージ が、売れる、ということそのものが、僕には魅力的じゃない何かだったのです。(もちろん、売れたいと思おうが思うまいがどっちみち売れてねえだろ、とも思いま す。) このレビューで行うことは、ただ音楽を一生懸命聞く、ということです。結論をいえば、それが一番足りなかったことでした。聞くことは他者を理解することであり、 必然的に対話になります。歌うことに意味はない。けれど聞くことには意味がある。歌うことは一人でもできる。けれど聞くことは一人ではできない。必ず歌う人がそこ にいる。聞くことは必ず対話であって、寛容さや注意深さや、人間にとっての成熟も、聞くことを通じて得られる。みんなが歌えたとしても、聞くことができる人間がい なければ、魅力的な場=社会にはなりません。僕らはいまこそ「聞く力」を使って音楽の場を再設定すべきなのです。 |