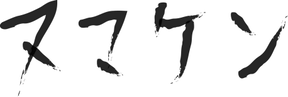|
・久しぶりの更新。内にこもっているようで、単に外に表出しなかっただけの期間でいたかもしれない。その反省で、むしろ内に内に、自己内省をえぐりはじめた。そもそも、そうやって内側から取り出したものがなければ、どんな表現も根拠をもてなかったのに、その作業をしばらく甘くみなしていた。コクヨのA4の青いノートにボールペンでぐねぐねと書き連ねていく。
・書く過程で、書く前は思いついていなかったいくつかのことがらが行き当たる。震災のとき、周囲のバンドマンで何人かが、音楽をやめようとした。逆に、震災で奮起して、募金をつのったりしていた人物たちもいる。僕は、そのどちらにもならなかった。後者のような良心的な振る舞いに、憧れながらたじろぐ感覚はあったかもしれない。が、より違和感をおぼえたのは前者の「音楽をやめようとする」人々に対してだった。僕は、いま歌うべきなにものも見いだせないとしても、それを探そうとしつづけるべきだとおもっていたし、それができないなら他のなにをやっても同じことだとおもっていた。今にして思えば、気負いがほとんどで、まだなにもやっていない者の言い分だったかもしれない。たぶん、いまもしあのときと同じようなことが起こったとしたら、同じ反応は抱けない気がする。 ほんとうに批判したいものがあったとしても、まだ僕には、それを言う資格がない。絶望も希望も、ただしくもつには、自分の来し方をただしく認識するしかない。ただ茫洋と過ぎる時間に、「望み」を溶かしてしまわないために。 ・現実から逃避するために、文章を書くのか。それとも対決するために書くのか。 音楽について書くことがためらわれるのは、具体的な活動を、総括する視点をうまく設定しえてないからだ。そしてそれは、現実とどう切り結んでいくか以前い、現実を見たくないという欲求のあらわれだ。さらにいえば、それを他人の目に届く衆目の場にさらすことの恥辱感へのおそれが抜きがたくある。それこそ、絶望的なひきこもり的心性かもしれない。(現代社会においてはますます発信しない者は透明な無存在になる) ブログを書く、とかツイッターに投稿するとか、そういうネット上のいちいちの振る舞いにも、僕はハードルを感じてしまう性質なのだ。それはメールの返信でもラインのやりとりでも同様で、たびたび迷惑をかける所以になってしまっている。 逆に、かえって表現し出すと過剰に表現しつづけてしまうときもある。連続してブログを更新したり、ツイッターを連投したり。 そこらへんが、僕のただいまの実存的風景の一部だ。そして自分のやりたいことを改めて考え直すと、この「実存」の「自由」をもっと増やしたい、「実存」の置かれてる状況をカイゼンしたい、という思いがあることに行き当たった。 少なくとも、「実存の平等」ということは、僕たちは考え得ることなのでないか、想像できることなのではないか、とおもうのだ。「生命の平等」と言ったとき、どうしても空疎に響いてしまうのは、地球上の生命を自己都合で摂取しているニンゲンがやはり自己都合でヒューマニズムを説いてるだけになってしまうからだ。存在倫理として、存在者として、人間の実存は平等である。 こういった次元に近づくために、むしろ薄汚いものも厭わずに露出すべきだと、僕はおもっている。自分に突きつけて、違和感を覚えるものに、その根拠を表明することは必要だ。自分がもっているたったひとつの実存を深く表現することなしに、他者の実存を尊重する態度は見いだせないから。 ・さて、僕は無学で無知なひとりの昭和終年世代の男にすぎないが、自分で見知った見識をもとに、考えつくったイメージを表明する権利はある。当然そんなことは言う必要もないことだが、何に対しても相対主義的な無力感を覚えるのは僕たち世代に顕著な傾向かもしれない。何かをする前に、もうそれに対する結論は出てしまっているような、そういう無力感が。 とすると、ただひたすら恥をかかないように、無難を有効策を打ち続ける方向を向きがちである。ただこれも僕には不満である。「承認」が一義的になってしまう行動様式は、最終的に被抑圧的に感じてしまうから。それよりもっと自由な空間を望みたい。それをつくるには、まず自分がやってみるべきなのだ。 消費者社会以後の論理じゃ出てこない、戦後間もないコトバの強度に学んで、そこから違った「戦後のルート」を想像し、これからの70年を反省的に見通してみたい。すなわち、『この世界の片隅に』ではなく、『野火』のルートを。 『この世界の片隅に』で、戦後は報われた。率直にそう感じた。馬鹿にも利口にもなりきれない僕なりの感想である。ただ、『野火』の方が残っていると感じるのだ。それも僕なりの感覚だ。この感覚を実際に推し進めるには、どうしたって「俺は勝手にやるんだ」という気概が必要である。それはある種の自己目的性だ。そのために、非承認をおそれる心を克己しなくてはならない。 『この世界の片隅に』で報われた戦後は、大衆としての戦後で、そこで大衆化できなかった問題が『野火』のルートにあるのだとおもう。 ・なにを言うにしてもツッコミに対する弁護を用意してしまう心性は、現在のネット社会が後押ししている心の様式のはずだ。このことに、窮屈さを感じるのは自然なことだとおもう。僕たちは特に、まだネットが普及しきる前に人格形成している世代だ。僕たちは社会がだんだん窮屈になってきているように感じるし、若者に流行っているサービスなどにももう疎くなっている。ネットが要求する様々なSNS的価値観や流儀に、疎外感を感じながら実存をもてあます機会が多くある。 かといって、じゃあリアルな空間、スモールワールドで自足した人間関係をもてるかといえば、僕の場合はそれもおぼつかない。結局、まずもって僕がもちうるのは、自分ひとりとの関係だった。それが基点になるし、それ以外に足場にできるものはなかった。だからこそ、思い切ってこの足場を確認しなければならない。 ・こうやって書いていて、音楽やライブや身の回りのライブハウスやミュージシャンに触れないことが、不自然じゃないかといつも気にはかかる。そこが切れているというのは、僕の課題かもしれない。書くことと歌うことが、互いに逃避関係として機能してしまっているとしたらまずいのだ。ただあまり具体的なことは、迷惑になるかもなあ、という経験からもくる忌避感はある。何かを書くということは、それ以外の何かを書かない、ということでもある。書かなくても考えてること、ノートにだけ書いていることもある。意識的に考えていなくても、思っていることはある。
0 コメント
|