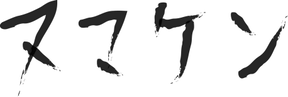|
・日記でもなんでもいいから、とにかく毎日、書きたいですよね。自分のために書くので、読まれるために書くのじゃなくて、でもこうして読まれることを待ってもいるというバランスが、我ながらちょろいもんです。
と、そういうことでもないんで。まったく、しっかし、「表現する」ってのはやっかいで、失敗ばかりです。きょうも、久しぶりにHPを点検してね、へんてこな動画とか、文章とか、とりあえず見えなくしました。なにをやっても、座りが悪いというか、バツが悪いのはね。こういうところなんで。と、と、と。 ・ライブをやってます。音楽してます。なんの話題をしようかね。ま、なんでもひとりごとですね。 北朝鮮がかまびすしいですね。っていう話題ですか?選挙ですか、解散? 話題はね、こちらのね、都合なんですよね。 荒野を、ゆく気分でね。発話が、伝える、が、そもそも不可能な気分におちいってね。 誰ァが炎上してますね。私、私、私をね、正しく出力しないとね、誰それジャあ、いけない。。。 ・人に読んでもらうこと。そのために整理すること。務。最近ビラをつくったんです。それの画像をあげよう、とおもったけど、やめた。 特別だったり、特別じゃなかったり、凡庸、変なだけ、そういう隘路におちいっては、罠、を社会側のポイントに見立て、それも誤謬で、いやんなる、またもやブルース、するね。 でけっこうそういうのが、あれなんです、循環、を催すというか。 「おもしろい」というのは、嘘なんですね。それは、自分、個人的に、ワタクシ的に、やっていくしかないしそうすべき。 だからその、手前、手前が問題だったんです。常に、表現の、そのする手前、手前に、全部あったんです的なオチでいこう。と。オチでいこうと思うんです。 悪意を、投げつける、と決め込んで立ちあったら、それなりに、強い、悪臭のするものは、できるかもね。いいんです。そのことはいいんです。 でもでもでもね、その人の文学の問題は、ずれこんで、ずれこみながら、だから演じ間違えながら、ジャンルをね、間違えてんだけど、でもその人なりに一生懸命、一生懸命としかいいようがない、ぐらい滑稽、なかんじの姿って、けっこう出力されんのよね。 それはけっこう残念だな。 ・もうちっとね、真面目な話がしたいです。だから北朝鮮の話ね。戦争よ。もう、なんだろう、俺たち監視されてる?みたいな。どこまでほんとでどこからデマかわからない。てね。それが、ポストモダン感覚じゃん?ちがう。 ちがう、というなら、ちがう、という根拠を合わせて提出しなきゃだね。元気にいくには、やっほう、いい気分が必要さ。 元気、いっぱい。 真面目な話か。推敲する気はないんだけ、まったく、緊張感なく、たれながすよね、だから、むしろ続かないのね。フォーマットが自堕落で、それが気分爽快の序説だとかなんとか、屁理屈ごねやがってちきしょう。 しっかし無意味な、ことしか書けない、書かないそればっか、というのも、一種の特技として、どこかの公的な機関に登録されうるとしたら、俺はそれを登録申請するか?として、その答えはNOだ。ノー。「ノー」と言えるのって、自由でタフガイ。 それはどうでもよく、 でもまあアグレッシブにすべるのは、必須だ。 ・久しぶりの更新。内にこもっているようで、単に外に表出しなかっただけの期間でいたかもしれない。その反省で、むしろ内に内に、自己内省をえぐりはじめた。そもそも、そうやって内側から取り出したものがなければ、どんな表現も根拠をもてなかったのに、その作業をしばらく甘くみなしていた。コクヨのA4の青いノートにボールペンでぐねぐねと書き連ねていく。
・書く過程で、書く前は思いついていなかったいくつかのことがらが行き当たる。震災のとき、周囲のバンドマンで何人かが、音楽をやめようとした。逆に、震災で奮起して、募金をつのったりしていた人物たちもいる。僕は、そのどちらにもならなかった。後者のような良心的な振る舞いに、憧れながらたじろぐ感覚はあったかもしれない。が、より違和感をおぼえたのは前者の「音楽をやめようとする」人々に対してだった。僕は、いま歌うべきなにものも見いだせないとしても、それを探そうとしつづけるべきだとおもっていたし、それができないなら他のなにをやっても同じことだとおもっていた。今にして思えば、気負いがほとんどで、まだなにもやっていない者の言い分だったかもしれない。たぶん、いまもしあのときと同じようなことが起こったとしたら、同じ反応は抱けない気がする。 ほんとうに批判したいものがあったとしても、まだ僕には、それを言う資格がない。絶望も希望も、ただしくもつには、自分の来し方をただしく認識するしかない。ただ茫洋と過ぎる時間に、「望み」を溶かしてしまわないために。 ・現実から逃避するために、文章を書くのか。それとも対決するために書くのか。 音楽について書くことがためらわれるのは、具体的な活動を、総括する視点をうまく設定しえてないからだ。そしてそれは、現実とどう切り結んでいくか以前い、現実を見たくないという欲求のあらわれだ。さらにいえば、それを他人の目に届く衆目の場にさらすことの恥辱感へのおそれが抜きがたくある。それこそ、絶望的なひきこもり的心性かもしれない。(現代社会においてはますます発信しない者は透明な無存在になる) ブログを書く、とかツイッターに投稿するとか、そういうネット上のいちいちの振る舞いにも、僕はハードルを感じてしまう性質なのだ。それはメールの返信でもラインのやりとりでも同様で、たびたび迷惑をかける所以になってしまっている。 逆に、かえって表現し出すと過剰に表現しつづけてしまうときもある。連続してブログを更新したり、ツイッターを連投したり。 そこらへんが、僕のただいまの実存的風景の一部だ。そして自分のやりたいことを改めて考え直すと、この「実存」の「自由」をもっと増やしたい、「実存」の置かれてる状況をカイゼンしたい、という思いがあることに行き当たった。 少なくとも、「実存の平等」ということは、僕たちは考え得ることなのでないか、想像できることなのではないか、とおもうのだ。「生命の平等」と言ったとき、どうしても空疎に響いてしまうのは、地球上の生命を自己都合で摂取しているニンゲンがやはり自己都合でヒューマニズムを説いてるだけになってしまうからだ。存在倫理として、存在者として、人間の実存は平等である。 こういった次元に近づくために、むしろ薄汚いものも厭わずに露出すべきだと、僕はおもっている。自分に突きつけて、違和感を覚えるものに、その根拠を表明することは必要だ。自分がもっているたったひとつの実存を深く表現することなしに、他者の実存を尊重する態度は見いだせないから。 ・さて、僕は無学で無知なひとりの昭和終年世代の男にすぎないが、自分で見知った見識をもとに、考えつくったイメージを表明する権利はある。当然そんなことは言う必要もないことだが、何に対しても相対主義的な無力感を覚えるのは僕たち世代に顕著な傾向かもしれない。何かをする前に、もうそれに対する結論は出てしまっているような、そういう無力感が。 とすると、ただひたすら恥をかかないように、無難を有効策を打ち続ける方向を向きがちである。ただこれも僕には不満である。「承認」が一義的になってしまう行動様式は、最終的に被抑圧的に感じてしまうから。それよりもっと自由な空間を望みたい。それをつくるには、まず自分がやってみるべきなのだ。 消費者社会以後の論理じゃ出てこない、戦後間もないコトバの強度に学んで、そこから違った「戦後のルート」を想像し、これからの70年を反省的に見通してみたい。すなわち、『この世界の片隅に』ではなく、『野火』のルートを。 『この世界の片隅に』で、戦後は報われた。率直にそう感じた。馬鹿にも利口にもなりきれない僕なりの感想である。ただ、『野火』の方が残っていると感じるのだ。それも僕なりの感覚だ。この感覚を実際に推し進めるには、どうしたって「俺は勝手にやるんだ」という気概が必要である。それはある種の自己目的性だ。そのために、非承認をおそれる心を克己しなくてはならない。 『この世界の片隅に』で報われた戦後は、大衆としての戦後で、そこで大衆化できなかった問題が『野火』のルートにあるのだとおもう。 ・なにを言うにしてもツッコミに対する弁護を用意してしまう心性は、現在のネット社会が後押ししている心の様式のはずだ。このことに、窮屈さを感じるのは自然なことだとおもう。僕たちは特に、まだネットが普及しきる前に人格形成している世代だ。僕たちは社会がだんだん窮屈になってきているように感じるし、若者に流行っているサービスなどにももう疎くなっている。ネットが要求する様々なSNS的価値観や流儀に、疎外感を感じながら実存をもてあます機会が多くある。 かといって、じゃあリアルな空間、スモールワールドで自足した人間関係をもてるかといえば、僕の場合はそれもおぼつかない。結局、まずもって僕がもちうるのは、自分ひとりとの関係だった。それが基点になるし、それ以外に足場にできるものはなかった。だからこそ、思い切ってこの足場を確認しなければならない。 ・こうやって書いていて、音楽やライブや身の回りのライブハウスやミュージシャンに触れないことが、不自然じゃないかといつも気にはかかる。そこが切れているというのは、僕の課題かもしれない。書くことと歌うことが、互いに逃避関係として機能してしまっているとしたらまずいのだ。ただあまり具体的なことは、迷惑になるかもなあ、という経験からもくる忌避感はある。何かを書くということは、それ以外の何かを書かない、ということでもある。書かなくても考えてること、ノートにだけ書いていることもある。意識的に考えていなくても、思っていることはある。 今日は ・今日はきのうの疲れがあり、特に目が疲れていて、しぼしぼ。またしてもいつもながらに、書き方にぶつかりあれこれ試行錯誤することに。もういいかげんこういうのも、もっとスムーズにいきたい。 なにかを伝達するためのブログじゃない、ということである。自分のために書いているのか。自己表出とめぐりあいたい。ここらへんは、微妙とおもわれるかもしれないが、でも詩というものは僕にとってそういう傾向のもので、自分の独り言のようでいて、そこに存在意義がある。 そういうことはなんとなく示しておきたい。 ((誰かになにかを、伝えるか?)) 「聞いてくれてありがとう。また、見てくれたらうれしいと思います。あの人もかっこいいよね(笑)もっとよくなるようにがんばります!」
ああ
ちきしょう ちきしょう ちきしょう というわけで今日はこれまで ・えーまあ、なんということだったっけ?あれが言いたい、これが言いたい。うかつにはじめてうかつに終わる。今日はうかつで、明日もうかつ。これでいこう、これで。
どうやって楽しみを構築するか、ということなんですね。 まず、楽しまなきゃあしょうがない。楽しくて、まじめ、というのが理想。楽しいだけでまじめになれないのは、少し物足りないのだ。 カオス。オウム。心の中が泡立って。
て、て、て、て。 カオスがやってくると、というか、カオスのなかに突入すると、そこはオウム的な、というかそれは単に連想のアレだけど、心が泡立つ。ようだ。言語を整理するのに時間がかかる。時間がかかるということは時間が要る。時間をつくるか盗まないといけないのだ。 『ドゥルーズ 解けない問いを生きる』
生成。卵。流れ。なにか固有の止まった固定的記名、でなく流れ。僕たちは流れ。常に。「最終的になになにになるんだ」とりあえず吹聴できるステータス、固定的な状態、達成、のようなものを重視すると、今度は流れ、連続性を分断しがちになる。 ポストモダン思想は役に立たないとおもっていた。それは破壊的で「人間」の諸価値を無化するようなもので、それだから敬遠していた。でもちがう。それはもっと時代の表現で、時代に応じたものの考え方のおおいなるヒントになる。そんなかんじに思えるようになってきた。ゲンロン0を読んだ効用で前提が整理できた感がある。それらは案外生き方を教えてくれる。つまり、無駄に怖がらなくていいし、こう考えれば前向きになれる、ここに突破口がある、みたいな風に。時代を先取りして、いま現れている問題、課題に答えようとしていた、そうともいえる。 あとはアイデンティティの問題。これに答えるには、吉本思想やサルトルの思想のようなものが、役に立つといえる。 僕は2012年まで糸井重里(ほぼ日)-吉本隆明のラインの言説に影響を受けてきた。そこでは左翼の内ゲバに至らないための自戒のようなものが強調されていた、ようにおもう。常に「いいことをいわない」とか、「無価値の価値」とかが言われ、「強いことを言ってみんなを従わせる」ことをさける注意みたいなものが常にあったように思う。それらは糸井さんの感性でありこだわり、あるいはトラウマ?に基づくものだった、たぶん。 糸井さん、ほぼ日から切り離した単体の吉本隆明はどうか。それはけっこう、単純なじゃない。ある意味、矛盾してるんじゃないか、ということを言っているようにもおもう。読み手によってイメージが変わる。宮台真司らが特に言う吉本隆明のポストモダン状況への感度の鈍さ、は、確かにそうともいえるけれど吉本思想、あるいは吉本文学とか吉本世界の全体性の一部をあげつらってる、とも同時にいえてしまう。露出が多いのだ。別にテレビによく出てたとかではないけど。出した本が膨大で、特に90年代、00年代以降はばんばん出してたんじゃないか。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー #2017/05/09 13:08 当事者としての自分は、弾き語りをやっている人間で、ライブをやる人間で、ということになっている。でも一般的な意味で批評意識は有意義だ、ということ。 石川さんのNewsPick興味深い。うかつにはじめない、おわらない。まあうかつにはじめたりすることもあっていいんだろうとはおもうけど。ただ準備、ふりかえりはたいせつだ、ということ。 生成すること。流れがたいせつだ、ということと、それでもやはり人間は区別しながら認知するはずで、その機能が意味を認識させてもくれるはずだ。まあ両方が大事ということになる。 |