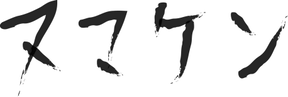|
しかし、悲観的なことばが必ず正しいとはかぎらない。むしろそれもバイアスがかかっている。現実がこうなったことへの反応としての悲観主義化という側面もあるか。現実を肯定しつつ道筋をみいだしていく類いの思想はいまありうるか。それはリバタリアニズムになっちゃうのか。
マストドンはどうかしらないが、とりあえず自分の空間を広げるというのが目下やるべきこと。ツイッターはだから利用したい。HPとツイッター、かな、いまのところは。WEB空間はそれでいい。YouTubeもそろそろあげたい。サウンドクラウドもやらないとミュージシャンだと思われないな。 そうするともっと野心的な作品もつくりたくなってくる。ちょいと前はそういった意欲もあったけれど、今年になってからは純粋に真面目に考えることが多い。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 今日は仕事がイベントで、だからリズムがおかしい。帰ってきてからブックオフに行き3冊購入。「シリーズケアをひらく」の『当事者研究の研究』がよさそう。これは、ミュージシャンにも適用できる、というか自分にも。俺の当事者研究。 「具体的な自分の実感をことばにすること」というくだり。そこに、ポエジーも宿るとおもえる。心の動きを記述。身体の反応をことばにする。 自分がその場にいられない、なんとなく疎外されたような、胸のあたりが落ち着かなくって、ひとりにならないといけないけどひとりになりたいわけじゃなく、ほんとうは共有できればいいのだけど、共有はしたくないしできない。そういう場面がある。そういうとき、それはこらえ忍ぶしかないのだけど、その体験をことばにすることができたら、なにかの一歩にはなる。事後的な共有への一歩になるかもしれない。人間とは、表現することによってつながりうる存在なのだ。 すべての本は表現だ。この文章もしかり。書き手はなにがいいたいか。なにを欲しているのか。メタメッセージとメッセージ、あるいは本音と建前。 SNSやら、いまどきのべき乗世界、スケールフリー、資本のそれに向かいあってこちらの心がくらってしまうとき、そこにも具体的なことばの表現余地がある。それらはまだ表に出ていないかもしれない。SNSがむかつくんだ、なんて、言ってみてもいいはずだけどそれも紋切り型と受け取られる。紋切り型ではない通路を経なければ。 いまビデオニュースの更新メールが入ったけど、ビッグデータに支配されないために、か。たとえばこうやって書く僕の文章によって僕の人格データが蓄積され、ネット履歴によって蓄積され、購入履歴、入力した単語、クリックしたいいねによって蓄積され、会社や政治?に利用される、というようなイメージだろうか。僕たちは動物だ。管理されている。こういう現実認識から「抵抗」のモチーフも生まれてくる。ただどこまで妥当かよくわからない面もおおい気がする。 「肯定する思想」というもので、未来性ある議論は不可能だろうか。それは間違いの素だろうか。最小単位なら肯定できる、ものもあるとして、それを出発点にできるならば。 歴史はかなり進んだ。人間社会は後期だ。というわけで、「ゼロ点」が見いだしづらい、ということはないか。当事者研究的方法でゼロ点が確認できるのでないか。べき乗でなく正規分布、ビッグデータではなく生身、そっちにもう一度ものさしを合わせなおす。 こういったことも散々言われ続けていることにすぎないかもしれない。ただ実存(の安定継続可能性)に必要な現実認識は、そこにゼロ点が含有されてないといけないとおもう。骨がなく服を着てボロボロくずれる、ということがないように。 出会いは偶然、別れは必然。10代、20代、偶然の経験、自分の判断でそれと距離をとったり。文学は後ろ歩きで前に進む、いいかえれば必然を重視する。
ただ、偶然が生ずるのは条件がいる。誰が偶然を用意したか。親、社会環境、自分の選択。 30才になる日というのは、偶然を重ねたうえで自分がなにを選択するか。もう処女性はない、そのうえでの選択は、自分自身の必然をおりこんだものになる。 誰の30才も祝福されていいように。その人の必然をみとめる。 ただこの「必然」もだんだん単純なものになっているのかもしれない。文学を軸にみれば明らかに単純になっている。宮台がいうように高次的から低次的へ。それは、意識の退化か。 意識が高次的であるとは、いかなる時代への準備適応だったのだろうか。かつての文学はなんのために重みをもっていたのか。敗戦の重み?戦後のねじれと高度成長の苦悶? なにはともあれ、そういった戦後文化の「子供たち」たる僕らは、その意識をもって、いまなにをなすべきか。その意識が生き延びていく道を探るのか。それとも意識は絶滅するか。 「これからはコミュニティ・ファーストだ」なんていったって、いい景色が想像できない。 東浩紀がいう「敵の似姿にならない」はとても共感。けれど僕はそうしてきて、それをある種逃げ口上にも使ってきた。そのことの反省もある。どこからどこまでが敵であり、どこまでが自分も使っていい範囲なのか、などの整理は必要だ。ただ、やはり高度であることを真正面から試みる、という姿勢が、回り回って一番有効だというかんじがする。それは『ゲンロン0』もそうだろう。 これができるのはポストモダニストの意識を生きてきたゆえだろう。根本的な必然性を自らに問うくせがあるから。そもそも、なぜそれをするか。そもそも、そもそも。「そもそも」を言わなければならないし、それをどれだけ説明できるか、問うてきたか。 文学でも音楽でも、重要で高度なことを伝達できるとおもう。そのことを忘れてもあきらめてもいけない。逆にいえばわりと勝手にあきらめてるのかもしれない。ほんとに高度なことを試みたためしがあるか。方法論ばかりで、いかに勝つかというゲームだけしか見えないようになっているのは、おかしな話なんだ。 そこらへんが「誤配」ということにつながってくるだろう。かつて「はじめての中沢新一」なるコンテンツがほぼ日にあったが、ああいうのがおもしろかった。ああいう誤配って、ほぼ日は誤配のサイトだった。ああいう誤配はいまない。それが「信用」だろうか。なにかが微妙に、けれど決定的にちがうのではないだろうか。 一瞬誤配で夢をみれた時代があったのだ。それを知れたのは幸運だったとおもうしかない。 時代の方向性を修正するというか、かつてあった可能性をもういちどやる、というような。そんな試みもみたい。あっていい。なにが潰えたか。民主党政権、震災前後で決定的になってしまったかな。 哲学にできること。いま支配的なゲームとは別のゲームを構想する。あるいは支配的なゲームを相対化する。『ゲンロン0』のような本。批評や思想はそうだろう。たぶん、近代社会のバランスとしては経済の上位に知識人がいたほうがいい。経済は「動物」の世界で「自然状態」である。いつでも上からの、人間からの視線がなければ、自然状態は全体化されるのみである。ボス猿が権益をもつのみだ。 哲学も「話」だった。書かれたもの以前に話されたこと。話す、ということは重要だし可能性がある。 そもそも論がもっとも大事。なぜ、意識は高次化されねばならないか。いや、ねばならないということはないのだ。けれど、人間は本来複雑な存在で、その実存が満たされるためにはそれ相応の手続きが必要とされるはずなのだ。「動物的な人間」が前面に出ていたら、目の前のエサを無限循環で食い続けるようなサマもありうる。それをやめる。さける。さけたうえで、自分自身の実存のもっとも問題となる部分へ目をやる。 そういった営みは高次化された意識が備わってないとどだい無理な話だ。では「自分自身の実存のもっとも問題となる部分へ目をやる」必然はなぜあるのか? こういった問いに答えきるのはむつかしい。「人間」を「近代的自我」ととらえてまがりなりに培ってきた僕のことばも、端的に古くさいかもしれない。 それは自分の「偶然の条件」ですね。つまり、どこに生まれ、どういう親のもとで育ち、誰と出会い、なにをおもい、どんな環境をもつか、というもの。そのいくつもの条件のぜんぶが自分という人間の固有性をかたちづくるわけです。そこから文学的な意味での可能性というのは出立するはず。 こう考えると、誤配というのは、つまり「偶然の子ども」をもつには、高次化された意識がないといけない。ひらたくいえば芸術家、表現者になるには意識が貧弱じゃお話にならないということになる。 ここらへんのことは「大衆の原像」とからめてよくよく肝心なところ。いつまでたってもむつかしいところ。 意識がない、動物、宮台のいう説明も納得するが、一方でメタ意識のようなものが上がっている領域もあるとおもう。メタソング、自虐、高次化された意識がおりこまれたサブカルチャー。ただ、身体反射に近いものがおおく、そこから大きい話になかなか展開しない。 高次化された意識は本来、大きい話に向かうものだった。それが身体感覚に閉じてしまった。最果タヒを思い出す。いまの時代における文化のありかた。詩、というよりは、なにかもっと別な、、、。 大きい話をする人、大きい話のできる場がないと、大きい行為もできないし大きい問題も解決されないのだ。これがおもいあたる重要問題。高次化→大きい話→問題解決。誰かが問題に対処しなければならない。いままで誰かが問題に対処してきた。いまこれからそれがいなくなるのか?だとしたら未来はこない。 いま朝。ぼーっとする。風呂にはいった。出来事を淡々と。それが詩のあわいになる。なにかを予測して事前に恐れるこころというのはなかなか離れない。それでも待っていれば時間がすぎていく。
------------------- 内向きのまま、外に出る、という姿勢がいいんだろうな、自分には、とおもうた。外に出る、外向きになる、と、外に合わせる姿勢になる。それはちがった。 たぶん、自分の「仕事」をストックさせていく意識でいければいいんだ。フローのなかで最大の効果を狙う、というのでなく。 昔のWEBはそうだった。おおむねホームページというのはアーカイブするものだった。「電脳的漫画論」とか(マンガ批評サイト)よく参考にしてマンガを買った。 いつしか拡散し動員するためのWEBばかり目立ってきたけど、本来もっと勝手にやっているというか、個人的なストックコンテンツを公開する、というところにおもしろさと自由度があったようにおもう。 昔のWEBは好きだったし、おもしろかった。いまはWEBも社会そのままというか、むしろWEBが社会というか、評価経済的な性質がとにかく全面的に前面に出ていて、それがつかれるし、異和する。 昔がよかった、という話ではない。昔の方法をいまやってみると、いまだからこそおもしろくなる、というアイデアの話だ。現状追認と先取りの競争だって、本来の倫理的な正当性が備わっているわけじゃない。わけじゃないのに、人はそれを正当だとおもいたがる。そこに関してはオルタナティブでありたいとおもうし、そうでなくてはならないだろう。 「自分に対する自己影響を第一義とする」という例の原則をやってみる、と。つまり、そのストックは自分のためのストックなんだ、ということが自由度をあげるミソなのだとかんじるようになってきた。妙に利他的な言説にひっぱられすぎてはいけなかった。それは方便であり、よくて片面の真実にすぎない。今上天皇がマニアックな動物の生態に詳しいような、そういうたぐいのこだわりがいいんだとおもうし、そこを主張してよい。 見いだしうるべき場所はある。やるべき余剰はつねにまっている。 東浩紀が言っていた「敵の似姿にならない」ということが、たしかにそうだな、とおもえる。 日記
2017/04/28 02:58 今日は新曲を練習した。16分の裏のノリで演奏させたい、とこだわっていたけど、どうももっと白玉で歌と曲全体の波を勘定して演奏したほうがよさそうだった。もう帰りたい時間だったけどはまってしまった。 演奏は、欲張ったら見失うものがあるんだとおもう。そう考えると、いつも欲張っている。あるいは単純に思い違っているだけか。もっと簡単で効果的な演奏があるのだ。 ニューズピックスの東浩紀と宮台真司の対談がおもしろかった。ゲンロン0も読んだし、東浩紀に共感率が高い。宮台の「なりすまし」も印象にのこった。ふたりの対談はおもしろい。 コメント欄のほうはふたりに否定的な意見もけっこうある。やはり、ビジネスパーソンらしい。 落合陽一のポストヒューマンぽい話は、やはり脅威を感じる。宮台さんは「主体」の話をしてくれるが、近代的自我のようなものはもうおしまいなのだろうか。 AIの時代になっても人間の実存は消えないし消せないだろう、とおもう。ただ価値観は変容していくだろう。その実存を手当するもの、と考えたって、高次的対応と低次的対応はちがう。結局ファストフード、サプリメントのようなものばかり増える。 ただメタ意識のようなものは一般化していっているような気はする。それとも、ネット社会に適応していてそうなっているだけか。 夜、吉本隆明の講演をすこしきく。質疑応答が本編より長いのが通例らしいが。若者?の質問を丁寧にきく吉本隆明は、すごいなとおもった。1987年ごろのもの。 |